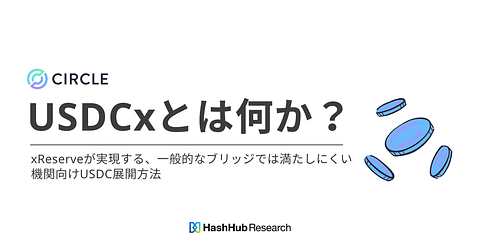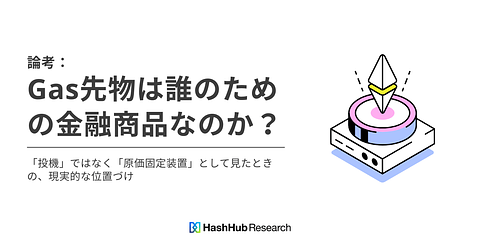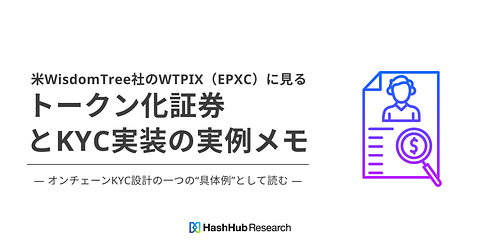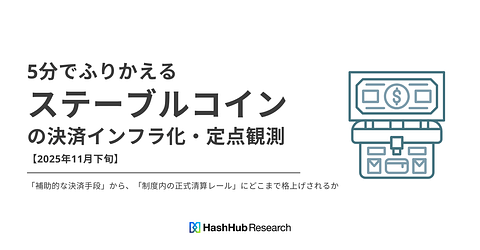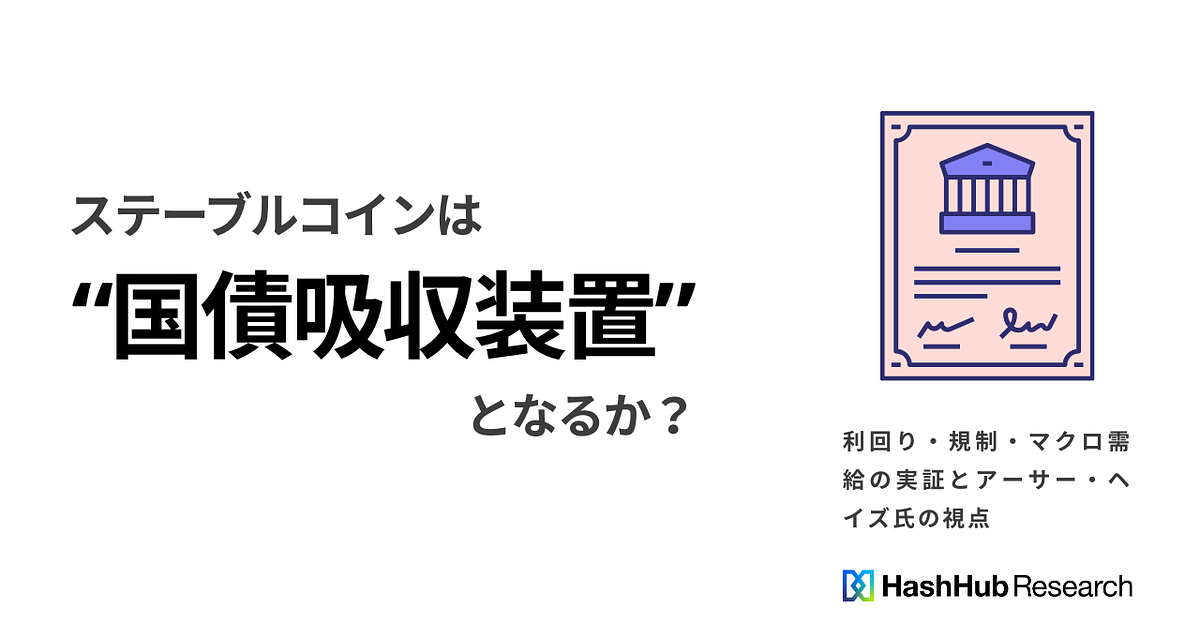
ステーブルコインは“国債吸収装置”となるか?利回り・規制・マクロ需給の実証とアーサー・ヘイズ氏の視点
2025年07月12日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- ステーブルコイン発行体の収益モデルと主要プレイヤー比較
- 準備資産の運用益に基づく収益
- ステーブルコイン発行体による国債市場への影響(“Quid Pro Stablecoin”の視点)
- Arthur Hayes氏の提起したシナリオ - カネと規制のバーター
- 米国債市場への需給・政策インパクト
- 需給面
- 政策面
- 市場リスク
- 日本市場への影響
- 総括
ブロックチェーン上で法定通貨の即時決済と自動化を実現するステーブルコインは、暗号資産の実験段階を越え、国際決済インフラと国債需要を同時に取り込む巨大な金融レイヤーへ急速に変貌しています。裏付け資金を短期米国債等に振り向けることで発行体は預金を凌ぐ利回りを確保し、CircleやTetherは金利収入だけで数十~百億ドルの利益を計上しました。2025年にはPayPalが保有者に年3%超のリワードを付与し、利回りを利用者とシェアする競争も本格化しています。
一方、Arthur Hayesは“Quid Pro Stablecoin”で、大手銀行が預金をトークン化して短期国債を買い支える構図を「国債吸収装置」と指摘し、数兆ドル規模の新需要が米財政を下支えすると試算しました。日本でも資金決済法改正により準備資産の50%を短期国債で運用できる余地が生まれ、米国ではGENIUS Actが銀行主導の発行体を想定した連邦規制を整備中です。
中央銀行は金融安定と決済効率、財務当局は国債安定消化を狙い、発行体・金融機関との利害が収斂しつつあります。
本レポートは①収益モデル、②国債需給インパクト、③日米規制とマクロ環境の連動をアーサー・ヘイズ氏の“Quid Pro Stablecoin”を参考にしながら考察します。
関連レポート
ステーブルコインの市場動向、二極化する市場と規制に関する米国と日本のアプローチとは
一方、Arthur Hayesは“Quid Pro Stablecoin”で、大手銀行が預金をトークン化して短期国債を買い支える構図を「国債吸収装置」と指摘し、数兆ドル規模の新需要が米財政を下支えすると試算しました。日本でも資金決済法改正により準備資産の50%を短期国債で運用できる余地が生まれ、米国ではGENIUS Actが銀行主導の発行体を想定した連邦規制を整備中です。
中央銀行は金融安定と決済効率、財務当局は国債安定消化を狙い、発行体・金融機関との利害が収斂しつつあります。
本レポートは①収益モデル、②国債需給インパクト、③日米規制とマクロ環境の連動をアーサー・ヘイズ氏の“Quid Pro Stablecoin”を参考にしながら考察します。
関連レポート
ステーブルコインの市場動向、二極化する市場と規制に関する米国と日本のアプローチとは
ステーブルコイン発行体の収益モデルと主要プレイヤー比較
準備資産の運用益に基づく収益
現在、法定通貨連動型ステーブルコイン発行事業者の主な収益源は、ユーザーから預かった法定通貨の裏付け資産を安全資産で運用することによる利息収入です。
USDC(Circle)
例えばUSDコイン(USDC)を発行するCircle社は、2024年の約17億ドルの収益のほぼ全てを準備金の運用益に依存しており(金利収入が収益の99%以上)、Circle社の準備金は主に米国短期国債と現金同等物で構成され、同社はUSDC準備金の利息収入の50%を米大手取引所Coinbase社と共有する契約を結んでいます。
これはUSDC流通拡大においてCoinbaseが主要パートナーであることの表れであり、USDCの流通量に応じてCoinbase社が受け取る利息収入も増減します。
これはUSDC流通拡大においてCoinbaseが主要パートナーであることの表れであり、USDCの流通量に応じてCoinbase社が受け取る利息収入も増減します。
USDT(Tether)
最大手ステーブルコインUSDTを発行するTether社も同様に準備金の運用益を主利益源としています。同社は準備金の大部分を米国短期国債で保有しており、その額は2024年末時点で約1,130億ドルに達し、世界有数の米国債保有者となっています。
この運用によりTether社は2024年に純利益130億ドル超を計上し、約70億ドルの利息収入を得たと報告されています。得られた利益は企業の自己資本や準備金バッファとして積み増されており、発行済みUSDT保有者への利息分配は行われていません(2024年末時点で準備金超過分は70億ドル以上)。
つまり利息収益は発行体の内部留保や株主利益となり、USDT保有者は依然利子の付かない現金同等物としてUSDTを利用する構図です。
各社報告より筆者作成
この運用によりTether社は2024年に純利益130億ドル超を計上し、約70億ドルの利息収入を得たと報告されています。得られた利益は企業の自己資本や準備金バッファとして積み増されており、発行済みUSDT保有者への利息分配は行われていません(2024年末時点で準備金超過分は70億ドル以上)。
つまり利息収益は発行体の内部留保や株主利益となり、USDT保有者は依然利子の付かない現金同等物としてUSDTを利用する構図です。
JPMorgan銀行(JPM CoinおよびJPMD)のモデル
2025年には、パブリックなブロックチェーン(Coinbase社のBaseチェーン上)で預金トークン「JPMD」を実証実験的に発行開始しました。
関連レポート
J.P.モルガンが預金トークン「JPMD」をパブリックブロックチェーンに展開する背景
JPMDは銀行預金を1:1でトークン化したもので、従来のフィンテック系ステーブルコイン(準備金として国債等を第三者保管する仕組み)とは異なり「銀行預金そのもののデジタル版」と位置付けられています。
JPMorganのブロックチェーン部門責任者はJPMDについて「既存の金融システムに統合された優れた代替手段」であると強調しており、現段階では機関投資家限定の試験運用ながら将来的な本格導入に含みを持たせています。
現時点でJPM Coin/JPMD保有者に対する利息支払いは公表されていませんが、Arthur Hayes氏はJPMorganが顧客預金をステーブルコイン化して準備金を国債運用することで「銀行はコンプライアンスコストを下げつつ利益を増やし、預金資金を米国債に回すことができる」と指摘しています。
言い換えれば、大手銀行発行のステーブルコインは銀行にとって預金の新たな活用ビジネスとなり得るという視点です。Hayes氏の試算によれば、仮に銀行が預金をステーブルコイン化することで自己資本規制上優遇される米国債保有を拡大し、さらにFRBの準備預金金利政策が変更されれば、合計で10兆ドル規模の国債購入余力が銀行側に生まれる可能性があるとされます。
以上のように、フィンテック企業型(Circle社やTether社等)と銀行型(JPMorgan等)でアプローチの違いはあるものの、準備資産から生じる利息収入を収益源とする構造自体は共通しています。その利ザヤ配分の方法(ユーザーへの還元か発行体の収益とするか)やリスク管理手法に各社の戦略の違いが表れている状況です。
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。