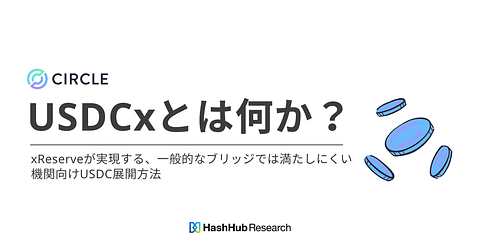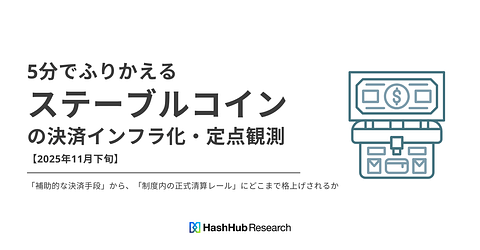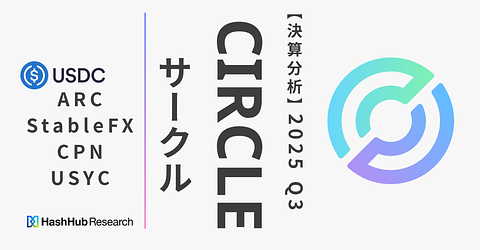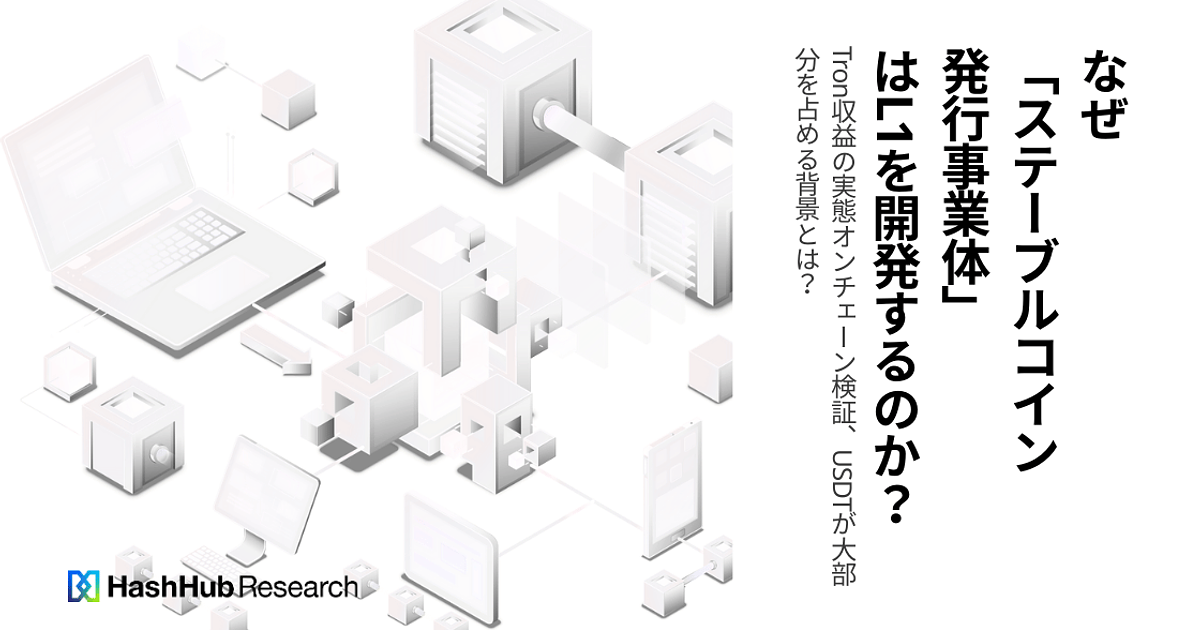
なぜステーブルコイン発行事業体はレイヤー1ブロックチェーンを開発するのか?|Tron収益の実態オンチェーン検証、USDTが大部分を占める背景とは
2025年08月25日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- Tron収益の仕組み
- データが示す「USDT一極集中」
- 経済的帰結:発行体にとってのインセンティブ
- CircleのArcとTetherのPlasmaへの関連
- ただしTronだけの特殊事例ではない
- 総括
なぜいま、ステーブルコイン発行事業者は自らレイヤー1(L1)を開発し始めているのでしょうか。その問いを理解する鍵は、既存のL1がどのように収益を上げているかにあります。
2025年現在、TronはEthereumを凌ぐほどの収益を誇るブロックチェーンとして際立った存在となっています。Token TerminalやDefiLlamaのデータによれば、直近30日のTronのプロトコル収益は約6,200万ドルに達し、Ethereum(約1,500万ドル)、Solana(約450万ドル)などを大きく引き離しています。
https://defillama.com/revenue?category=Chain
さらに、他のL1チェーンとの365日比較では、およそ75%を占め、圧倒的な収益規模を誇っていることは注目に値します。
https://tokenterminal.com/explorer/markets/blockchains-l1/metrics/revenue
収益規模だけを一見すると、Tronは多様なDAppsが繁栄し、Ethereumを超える経済圏を築き上げたかのように思えるかも知れません。しかし実際の内訳を追うと、Tronの収益の大部分はUSDT送金に依存していることが明らかになってきます。
さらに、他のL1チェーンとの365日比較では、およそ75%を占め、圧倒的な収益規模を誇っていることは注目に値します。
収益規模だけを一見すると、Tronは多様なDAppsが繁栄し、Ethereumを超える経済圏を築き上げたかのように思えるかも知れません。しかし実際の内訳を追うと、Tronの収益の大部分はUSDT送金に依存していることが明らかになってきます。
本レポートでは、この構造を検証し、その上でなぜCircleやTetherといったステーブルコイン発行体が「自前のL1開発」に乗り出すのか、その経済的な背景を読み解きます。
なお、自前のL1開発へ乗り出す背景には、経済的な背景だけでなく、規制対応、ユーザー体験なども複合的に絡まる狙いがあります。本レポートではそれらの内容は簡潔に触れるに留めています。なぜなら、規制やユーザー体験といった要素はもちろん無視できない重要な文脈ですが、それらは最終的に「経済的なインセンティブ」を補強する要因として機能しているに過ぎないと解釈しているからです。
なお、自前のL1開発へ乗り出す背景には、経済的な背景だけでなく、規制対応、ユーザー体験なども複合的に絡まる狙いがあります。本レポートではそれらの内容は簡潔に触れるに留めています。なぜなら、規制やユーザー体験といった要素はもちろん無視できない重要な文脈ですが、それらは最終的に「経済的なインセンティブ」を補強する要因として機能しているに過ぎないと解釈しているからです。
Tron収益の仕組み
TronはEthereum型のガスモデルを踏襲しつつ、EnergyとBandwidthという独自のリソース設計を導入しています。スマートコントラクト実行にはEnergyが必要で、不足分はTRXをバーンすることで補われます。これがプロトコル収益として計上される仕組みです。
つまり、収益が積み上がるためには「Energyを大量に消費する取引」が継続的に行われる必要があります。では、実際に何がTronのEnergyを消費しているのでしょうか。
データが示す「USDT一極集中」
Token Terminalの「Trending Contracts」を見ると、答えは明白です。
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。