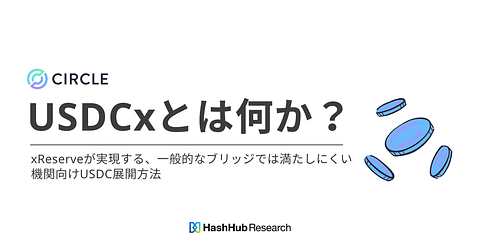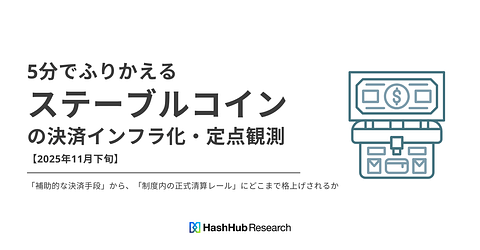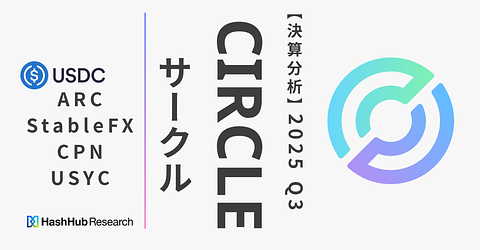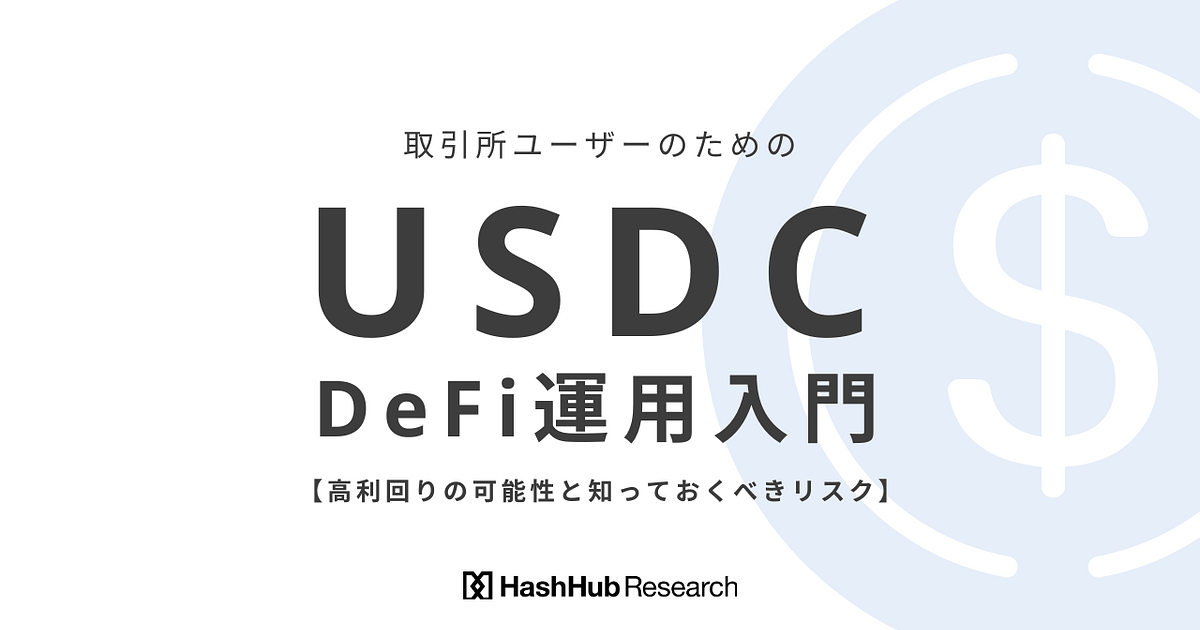
取引所ユーザーのためのUSDC DeFi運用入門:高利回りの可能性と知っておくべきリスク
2025年04月16日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
1. はじめに:USDCとDeFiの世界へようこそ
目的と対象読者
本稿は、中央集権型取引所(CEX)での暗号資産取引には慣れているものの、DeFi(分散型金融)については初心者である日本のユーザーを対象としています。特に、米ドル連動型ステーブルコインであるUSDC(USD Coin)を保有し、その新たな活用方法としてDeFiでの運用に関心を持ち始めた方々に向けて、基本的な仕組み、具体的な運用方法、潜在的なメリット、そして最も重要なリスクについて、具体的かつ分かりやすく解説することを目的としています。
本稿の位置づけ
DeFiは、従来の金融システムのあり方を変える可能性を秘めた革新的な分野ですが、同時に、これまでの金融サービスには見られなかった特有のリスクも内包しています。本稿は、特定の金融商品や投資戦略を推奨するものではなく、あくまでDeFiの世界を理解し、安全な利用のために不可欠な知識を提供するための一助となることを目指しています。DeFiへの参加を検討する際には、本稿で解説するリスクを十分に理解し、ご自身の判断と責任において行動することが極めて重要です。
免責事項
DeFiプロトコルの利用や暗号資産の運用には、元本割れを含む重大なリスクが伴います。スマートコントラクトのバグや脆弱性、ハッキング、プラットフォーム運営者の信頼性、規制環境の変化、市場の急変動、利用する暗号資産(ステーブルコインを含む)の価値変動など、予期せぬ要因によって投資した資産の大部分またはすべてを失う可能性があります。本稿で提供される情報は、いかなる投資助言または推奨を構成するものでもありません。DeFiへの参加は、ご自身の判断と責任において、十分な調査(DYOR: Do Your Own Research)を行った上で行ってください。
2. USDC(USD Coin)とは?:デジタルドルの基本
米ドルペッグのステーブルコイン
USDC(USD Coin)は、その価値が常に1米ドル(USD)とおおむね等しくなるように設計・運用されている「ステーブルコイン」と呼ばれる暗号資産の一種です。ステーブルコインは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)のような他の多くの暗号資産が抱える価格変動(ボラティリティ)の問題を解決し、価値の安定性を目指して作られました。USDCは、ブロックチェーン技術が持つ利便性(国境を越えた迅速かつ低コストな送金、プログラムによる自動化など)と、基軸通貨である米ドルの安定性を組み合わせることで、「デジタルドル」としての役割を果たします。これにより、価格変動リスクを避けながらブロックチェーン上で価値を保存したり、送金・決済手段として利用したりすることが可能になります(図1)。近年、日本国内の暗号資産取引所でもUSDCの取り扱いが開始されており、日本のユーザーにとってもアクセスしやすくなっています。
(※ステーブルコインは米ドル以外にもユーロや円などに連動したタイプも存在します。)
(※ステーブルコインは米ドル以外にもユーロや円などに連動したタイプも存在します。)
図1:USDCを用いた送金、決済、預金、トレード(出典:https://www.usdc.com/)
発行主体と信頼性への取り組み
USDCは、米国の有力フィンテック企業であるCircle Internet Financial社(以下、Circle社)によって発行・管理・運営されています。Circle社は、大手暗号資産取引所Coinbase社との協力のもと、2018年にUSDCをローンチし、以来、USDCを軸とした決済ソリューションやAPI提供など、デジタル通貨インフラ事業を展開しています。
USDCの価値の安定性を支える根幹は、その準備金の仕組みにあります。Circle社は、発行済みのUSDC総額と同等かそれ以上の価値を持つ米ドル相当の資産を「準備金(リザーブ)」として分別管理していると説明しています(図2)。この準備金は、現金および償還期間の短い米国財務省証券(短期米国債)など、流動性が高く安全とされる資産で構成されており、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNY Mellon)といった大手金融機関がカストディアン(保管・管理)を務めています。さらに、Circle社は透明性と信頼性を高める取り組みとして、この準備金の構成内容に関する証明書を、大手監査法人による監査を経て毎月公表しています。こうした厳格な管理体制と情報開示への注力は、規制遵守を重視する機関投資家などからの信頼獲得にも繋がっていると考えられます。
マルチチェーン対応
USDCは当初、イーサリアムブロックチェーン上でERC-20規格のトークンとして発行されましたが、その後、利用者のニーズやエコシステムの拡大に伴い、イーサリアム以外にもSolana、Polygon、Avalanche、Tronなど、多数のブロックチェーンネットワーク上でネイティブに発行・利用できるようになっています。これを「マルチチェーン対応」と呼びます。
このマルチチェーン対応により、ユーザーは各ネットワークの特性(取引手数料(ガス代)の安さ、取引処理速度の速さ、対応するDeFiアプリケーションの種類など)に応じて、最適なチェーンを選択してUSDCを利用することが可能になりました。例えば、イーサリアムのガス代が高騰している時期には、より安価な手数料で取引できるPolygonネットワーク上のUSDCを利用するといった選択肢が生まれます。
しかし、この利便性の裏側には、新たなリスクも存在します。特にDeFi初心者にとっては、送金時に正しいネットワークを選択するという、これまでCEXではあまり意識する必要のなかった操作が求められます。異なるネットワーク間でUSDCを送金しようとしたり、誤ったネットワークのアドレスに送金してしまったりすると、資産を永久に失ってしまう可能性があります。したがって、USDCのマルチチェーン対応は利便性を向上させる一方で、ユーザーには利用するネットワークを正確に理解し、慎重に操作することが求められるという側面も持ち合わせています。
【USDC関連レポート】
【USDC関連レポート】
- USDCの概要|投資家目線の特徴を踏まえた概要、日本における展望、ユースケースを考える
- ステーブルコインUSDCとUSDTの構造比較:信頼性・規制対応・流動性の観点から|デジタルドルの選定とリスク評価に向けた実務ガイド
3. DeFi(分散型金融)とは?:新しい金融の形
中央管理者のいない金融システム
DeFi(ディーファイ)とは、Decentralized Finance(分散型金融)の略称で、銀行、証券会社、取引所といった従来型の金融機関(中央集権的な管理者)を介さずに、金融サービスを提供・利用しようとする試み、またはそのエコシステム全体を指す言葉です。DeFiの世界では、個人間(P2P)または個人とプログラム(スマートコントラクト)の間で、貸付、借入、交換(スワップ)、保険といった様々な金融取引が直接行われます。
これらの取引のルールや実行は、ブロックチェーン上に記録された「スマートコントラクト」と呼ばれるプログラムコードによって自動的に管理・執行されます。例えば、「特定の条件が満たされた場合に、AからBへ自動的に送金する」といった契約をプログラム化し、人の手を介さずに実行することが可能です。
主要な特徴
DeFiは、従来の金融システム(CeFi: Centralized Finance)と比較して、以下のような特徴を持っています。
- 透明性: DeFiプロトコルにおける取引の記録やスマートコントラクトのコードは、基盤となるブロックチェーン(多くはパブリックブロックチェーン)上に公開されており、原則として誰でも閲覧・検証することが可能です。これにより、取引の透明性が高く、データの改ざんが極めて困難であるとされています。
- 自己管理: DeFiを利用する際、ユーザーは通常、自身の「秘密鍵」を用いて暗号資産ウォレットを管理します。これは、銀行口座のように金融機関に資産を預ける(Custodial)のではなく、ユーザー自身が資産の所有権と管理責任を持つ(Non-Custodial / Self-Custody)ことを意味します。
- アクセス性: DeFiサービスは、特定の国や地域、個人の属性(信用情報など)による制限を受けにくく、インターネット接続と対応ウォレットがあれば、原則として世界中の誰でも利用できる可能性があります。これは金融包摂(Financial Inclusion)の観点からも注目されています。
- プログラム可能性: スマートコントラクトを活用することで、既存の金融商品を組み合わせたり、全く新しい金融サービスを創造したりすることが可能です。レンディング、DEX(分散型取引所)、デリバティブ、イールドファーミング(流動性マイニング)など、多様なアプリケーションが登場しています。
- 効率性・低コストの可能性: 仲介機関を排除し、プロセスを自動化することで、理論的には取引手数料を低く抑え、サービス提供を迅速化できる可能性があります。ただし、後述するように、ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代)は変動するため、常に低コストであるとは限りません。
- 24時間365日稼働 : スマートコントラクトはプログラムによって自動実行されるため、銀行の営業時間のような制約がなく、原則としていつでもサービスを利用できます。
DeFiが持つこれらの特徴、特に「誰でもアクセス可能」というオープンな性質は、金融サービスをより多くの人々に届ける可能性を秘めています。しかし、この開放性は、規制当局から見ると、マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)、そして利用者保護の観点から大きな課題を提示します。匿名性の高い取引が可能であり、従来の金融機関のような本人確認(KYC)プロセスが必須でない場合が多いため、不正利用のリスクが指摘されています。各国規制当局はこの問題に対処しようとしていますが、DeFiの分散化された国境のない性質は、既存の規制枠組みの適用を困難にしています。結果として、ユーザーはイノベーションの恩恵を享受できる可能性がある一方で、法的な保護が不十分であったり、規制の変更によって利用環境が変化したりするリスクに常に晒されることになります。
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。