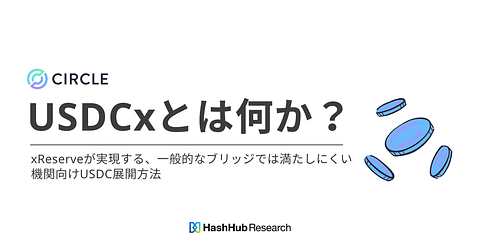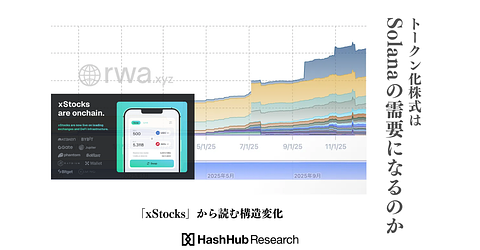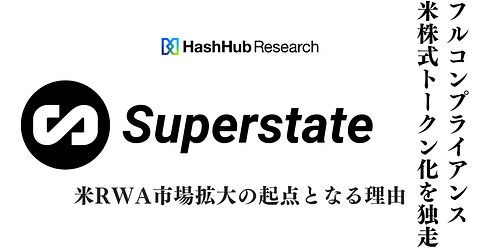Visa戦略考察:ステーブルコインによるオンチェーン信用レイヤーの主導権とDeFiの制度接続
2025年10月22日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 「DeFi」ではなく「オンチェーン金融」とするVisaの狙いと背景
- ステーブルコインベースのオンチェーン融資市場の成長と信用担保機能の変化
- 金融インフラ再編に挑むVisaの立ち位置と主要プレイヤーとの競合構造
- DeFiの伝統金融への侵食と金融機関へのインプリケーション
- 総括
このレポートは、2025年9月時点の情報をもとに、ステーブルコインが単なる決済ツールを超えて、新しい信用市場(オンチェーン融資)を形成しているという認識を示すものです。
Visaはこれを「DeFi(分散型金融)」とは呼ばず、Onchain Financeという新しい用語で再定義しています。その背景には、米国を中心とする制度整備の進展や、ステーブルコイン市場の急拡大があります。
Visaは、ブロックチェーン上の信用市場がいよいよ制度的規模に到達したと見ており、自らがその「標準レール」を担う意思を明確にし始めています。
本レポートでは、今回のホワイトペーパーを筆者の観点から意訳し、この内容を踏まえた筆者解釈と金融機関・事業会社に求められる戦略について述べます。
「DeFi」ではなく「オンチェーン金融」とするVisaの狙いと背景
Visaは今回のレポートで「DeFi」ではなく「オンチェーン金融」という用語を用い、分散型金融を既存の制度金融に組み込みやすい形で再定義しようとしています。
その意図として考えられるのは、規制環境や伝統的金融機関への配慮から、あえて「オンチェーン金融」とフレーミングし直しており、意図的なリブランディングだと思われます。
しばしば、無許可・無規制・高リスクとみなされる従来のDeFiのイメージから距離を置き、銀行など厳しく規制された組織にも受け入れやすい形で新たなオンチェーン型金融プラットフォームを位置付けようとしているのでしょう。
この背景には、近年各国で進むステーブルコイン規制の整備があります。米国では2025年に「GENIUS法(米国ステーブルコイン革新法案)」が成立し、ステーブルコイン発行に初の連邦規制が敷かれました。これにより銀行を含む金融機関がブロックチェーン活用に踏み出すための明確なルールが整いつつあり、Visaも15,000超の金融機関パートナーに対しオンチェーン金融への参加を促進する姿勢を示しています。
要するにVisaは、「オンチェーン金融」というより中立的な語を使うことで、規制当局や金融業界に対し、「これは既存制度と両立し得る新しい金融インフラなのだ」というメッセージを発信していると考えられます。
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。