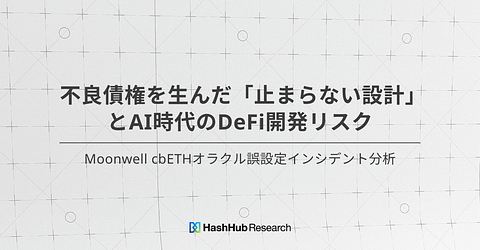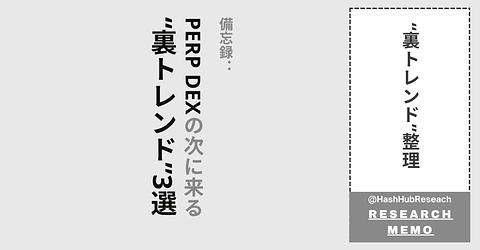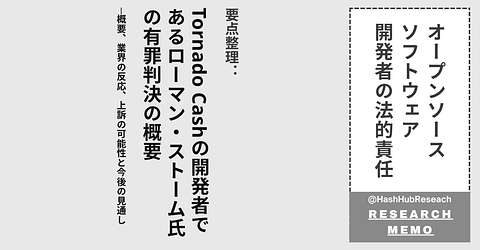DeFiのファンダメンタルズ・シーズンを考える:AavenomicsとDeFiトークンの中期バリュエーション評価をもとに
2025年03月15日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- なぜ、いまAavenomicsなのか?
- Aavenomicsの概要
- Aavenomicsの目的
- 主な変更の背景
- Buy and Distribute Programの仕組み
- AavenomicsとDeFiファンダメンタルズ・シーズンの到来を考える
- 1. DeFiの安定収益化と“BTC連動”からの脱却
- 2. 機関投資家の参入と評価指標の成熟化
- 3. “Winner Takes Most”と多プロトコル連携の可能性
- 4. 収益分配トークンの将来像:企業型経営とリスク管理
- 総括
なぜ、いまAavenomicsなのか?
Aaveは、Ethereum上の分散型レンディングプロトコル(当初はLEND)として出発し、現在ではマルチチェーン対応や独自ステーブルコインGHOの発行など、多岐にわたる領域で存在感を示し、DeFiプロトコルの主要プレイヤーと言っても過言ではありません。
https://defillama.com/(2025/03/13時点のTVLランキングでLidoに次ぐ2位)
こうしたAaveが、2024年後半から2025年にかけてのトークンエコノミクス大幅見直しにおいて「Buyback(トークン買い戻し)を含む収益還元策」を実施する方針であるAavenomicsを打ち出しています。
DeFiプロトコルによる買い戻しは、伝統金融における自社株買いにも似た手法で、トークン価格の底支えやホルダーへの還元効果などが期待されるものです。この提案が発表された際には、AAVE価格は20%ほど上昇したと報じられています。
しかし、「トークンを企業株式のように買い戻す」ことには賛否両論があり、実行の可否やその効果はプロジェクトの成熟度や財務状況、ガバナンスの透明性に強く依存します。
そこで本レポートでは、Aaveがどのような狙いと仕組みでBuybackを導入しようとしているのか、またAaveのトークンエコシステム全体を俯瞰しながら、投資家として着目すべきポイントを解説します。
また、HashHub Researchでは過去に、「多くの手数料分配形アプリケーショントークンは収益をあげていたとしても、なぜ中期でパフォーマンスが優れないか」というレポートを公開しました。
筆者は、上記のレポートの主張に概ね同意です。しかし、敢えて今回のAavenomicsの展開を踏まえた反論をするならどう主張できるか?を筆者独自の観点で考察し、本レポートをカウンターレポートとしてみたいと考えています。目的は、DeFiトークンを中(長)期的に投資対象として捉える場合の視点を読者に提案することです。
当該レポートを本レポートと併せてご覧いただくことで、DeFiプロトコルの取り組みとトークン価格への影響に関するダイナミズムに、より理解を深めることができるでしょう。
Aavenomicsの概要
その第一の目的は、プロトコルの成長に合わせてトークン価値の還元と持続可能なインセンティブ設計を実現することにあります。
Aavenomicsの提案には、Buyback施策以外のものも含まれる包括的な提案です。本レポートでは、網羅的な詳細は触れず論旨の中核であるBuybackに関連する点にフォーカスします。
Aavenomicsの目的
具体的には、
- AAVEトークンの配布効率を最適化(これまでばら撒いていたインセンティブを見直す)
- 流動性供給へのコストを削減しつつ必要十分なセカンダリ流動性を確保する
- 旧トークンLENDの最終的な処理
- Anti-GHOの導入・収益の再分配モデルの構築
- AAVEトークン予算(エコシステムリザーブ)の長期持続性を確保する道筋をつける
ことが主な目的として掲げられています。
要するに、プロトコルの収益をAAVEトークン保有者やステーカーに還元し、Aaveの経済圏全体の持続可能性と参加者のインセンティブを高めることが狙いです。
この変更により、従来は主にプロトコル運営資金としてプールされていた「余剰収益」をコミュニティに還元し、AAVEトークンに実質的な価値の裏付け(バリューキャプチャー)を与えることになります。
参考文献
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。