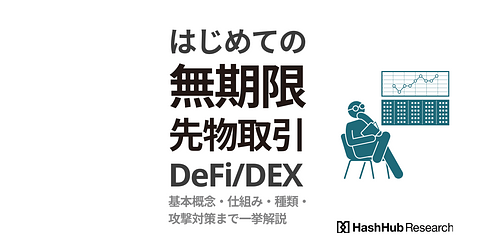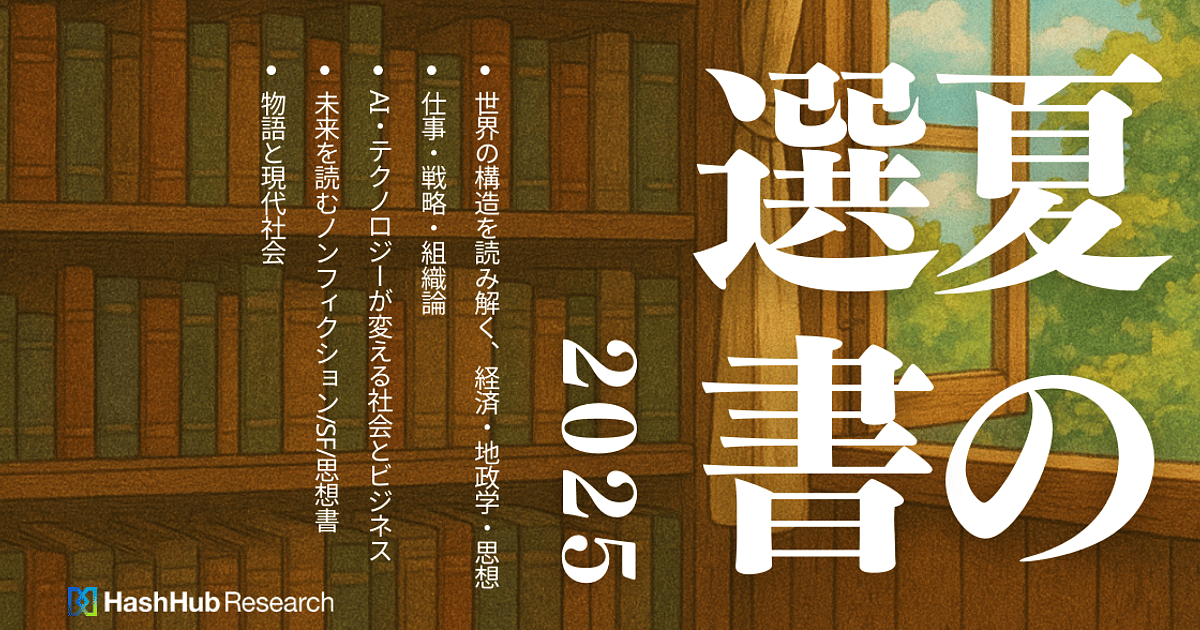
【2025年夏の選書】HashHubチームがこの夏読んでいる、またはオススメの書籍
2025年08月15日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
お盆休みは、普段読めない本にじっくりと向き合う絶好の機会です。HashHubチームでも、この期間を活かして知見を広げようと、メンバーそれぞれが「読みたい本」「読んでよかった本」を持ち寄りました。
この特集では、チームから寄せられた書籍やWeb記事をテーマ別に紹介します。AI、経済、未来予測から仕事の哲学まで、多岐にわたるラインナップです。きっとあなたの興味を引く一冊が見つかるはずです。
1. 世界の構造を読み解く、経済・地政学・思想
『2050年の世界 見えない未来の考え方』
- 書籍: 『2050年の世界 見えない未来の考え方』
- 推薦者: 加藤諒
古くはバビロニア天文学の天体運航予測から、新しくは天気予報や経済予測まで、古今東西、人間は未来を予測することに莫大なコスト(時間、労力、お金etc...)をかけてきました。それは、未来を予測することにより、物事を「有利」に進められるからです。コンピューティングの進化(古典的なコンピューティングのみならず、量子コンピューティングも含めて)に伴い、未来予測の精度は日に日に上がっていますが、25年後の未来ともなると、「予測してもまずその通りにはならない」でしょう。本書で述べられている予測も、「外れるものもあれば、当たるものもある」のだと思いますが、本書を読むことによって、読者諸兄・諸姉の旺盛な知的好奇心を満たすだけでなく、「未来への視座」を獲得することができ、ビジネスや諸活動の「次の一手、今打つべき一手」のヒントが得られるはずです。
『1985年の無条件降伏~プラザ合意とバブル~』
- 書籍: 1985年の無条件降伏~プラザ合意とバブル~
- 推薦者:derio
最近も40年の節目で話題になった「日本航空123便墜落事故」の重苦しい出来事から、ワシントン発の至急連絡を経てプラザ合意に雪崩れ込む瞬間を、当事者取材の距離感で描いた一冊です。出来事の羅列ではなく、外交・通貨・金融行政が絡み合う意思決定の遅滞と副作用を、失われた20年に至る長い射程で捉え直す内容で、日本経済史の勉強をしたいと思っていた私にとって非常に分かりやすい本でした。市場構造を規定するのは単独の出来事ではなく、制度の噛み合わせとタイミングだというインサイトも個人的に腑に落ちたのですが、全体的に読みやすさ・分かりやすさが一級品だと思っています。昨今の円安やトランプ関税についての歴史的背景を知りたい方や、経営・投資の意思決定に歴史的視界を求める方、政策過程の現場心理を知りたい読者におすすめです。
『アメリカ経済 成長の終焉』
- 書籍: アメリカ経済 成長の終焉
- 推薦者:Junya Hirano
『アメリカ経済 成長の終焉』は、長年世界経済を牽引してきた米国が抱える構造的課題を鋭く分析した一冊です。著者は、金融緩和と財政赤字に依存した成長モデルが限界を迎えつつあり、人口動態の変化、産業競争力の低下、格差拡大といった要因が持続的成長を阻むと指摘します。株高やドルの強さといった表面的な好調さの裏に潜む脆弱性を、歴史的データと具体的事例で浮き彫りにしている点です。米国の覇権はすぐには揺らがないものの、成長率低下は既定路線であり、その影響は世界全体に及ぶという視座は説得力があります。単なる悲観論に終わらず、再生のための政策や構造改革の方向性も提示しており、それらの内容は「アメリカは世界最強の経済」という一元的な見方を見直す内容です。
『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』
- 書籍: あの国の本当の思惑を見抜く 地政学
- 推薦者:Junya Hirano
『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』は、国際情勢の背後にある各国の戦略や利害を読み解く視点を養う一冊です。著者は単なるニュースの羅列ではなく、歴史的背景や地理的条件、経済的構造など多角的な要素を組み合わせ、各国の行動原理を分析しています。特に米中関係やロシア、欧州、中東など、現代のホットスポットを取り上げ、それぞれの「表向きの理由」と「本音の戦略」のギャップを明らかにしている点が印象的です。
私自身、地政学の書籍をこの数年何冊か読んでいますが、その中でも読みやすさと著者の視点どちらの意味でもおすすめできる1冊です。
2.仕事・戦略・組織論
『圧勝の創業経営』
- 書籍: 『圧勝の創業経営』
- 推薦者: 加藤諒
ドン・キホーテ創業者の安田氏が「最後の書」として※、日本を代表する創業経営者らとの対談を収録した本書ですが、サラリーマン経営者の端くれの私が読んでも、元気を頂いた一冊でした。まだまだここからっす。 ※安田氏は本年7月にメディアに対して、末期がんのご闘病中であることを明かされています。
『Webフォント実践ガイド Google Fontsではじめる 美しく機能的なタイポグラフィ』
- 書籍: Webフォント実践ガイド Google Fontsではじめる 美しく機能的なタイポグラフィ
- 推薦者: Hiroki Morita
リアルに文字を書く機会が減り、気づけば人生トータルでデジタルで文字打ってる方が多くなったと感じます。
筆跡はなくとも、デジタルの文章にも固有の表現、行間や感情、美的バランスが現れますよね。なんとなく「生成AIっぽい」文章も感じ取れたりしませんか?
本書では、あらゆるデジタルコンテンツの大元である「フォント」について学ぶことができます。
デジタルで制作・コミュニケーションすることが多い方々にオススメの一冊です。
筆跡はなくとも、デジタルの文章にも固有の表現、行間や感情、美的バランスが現れますよね。なんとなく「生成AIっぽい」文章も感じ取れたりしませんか?
本書では、あらゆるデジタルコンテンツの大元である「フォント」について学ぶことができます。
デジタルで制作・コミュニケーションすることが多い方々にオススメの一冊です。
3.AI・テクノロジーが変える社会とビジネス
AI 2027
- web記事: AI 2027
- 推薦者: Lawrence
元OpenAI研究者らが、2027年までのAIの浸透した世界を考察した記事。SFを楽しむ感覚で読めます。文中で登場するのは架空の企業ですが明らかに実在するAI企業が想定されています。あらゆることが効率化されるなか、働くとは、仕事とは、生きるとは、色々な点を思考することができる記事です。
古典『禅とオートバイ修理技術』が問うAI時代の「品質管理」
- 書籍: 禅とオートバイ修理技術
- 推薦者: masao i
急ぐという行為自体が、この二十世紀に蔓延している姿なのだから。何かを急いでやろうとすれば、もはやそれに対する気くばりはなくなり、すぐにほかのことに手を出したくなる。私は、ゆっくりと、しかも慎重かつ入念に解き明かしてゆきたい。[ロバート・M・パーシグ]
JALが年会費24万円の超高級クレジットカードを発表したものの、公式サイトの画像がAI生成による指の数の異常で炎上。この一件は、ブランドの信頼を大きく揺るがす結果に。(参考記事)
いや、わろてるけど他人事じゃないでしょ。現在の「AI活用≒効率化・生産性向上」を当たり前としたビジネス慣習がこのような事態を促したのであり、事の大小はあれど、この環境下を生きる誰もが直面していてもおかしくはない事態。
この騒動を目にして、ふと本書を思い出しました。この本は単なるバイク好きによるバイク好きのためのオートバイの修理技術を説くものではありません。専門家に委ねるのではなく、自らの手で機械に向き合うことを通して、物事の本質や「クオリティ(広義の品質)」とは何かを探求する哲学書(フィクション化された自伝)です。現代はAI(専門家の代替)やデジタルツールで効率化を謳いますが、JALの騒動は、その陰で本来不可欠な「気配り」が失われている現実を突きつけ、パーシグが説いた「急ぐ」ことの対極にある「入念に、慎重に解き明かす」という姿勢は、生産性至上主義に対する痛烈な批判として響きます。
AIの万能感に酔いしれ、一つのことに深く向き合わず、次々と別の作業に手を出す「マルチタスク中毒」とも言える現代の病。この病が原因で、私たちは品質に徹底的に向き合うための余白を失っているのではないでしょうか(もちろん品質をそこまで気にしなくてもいい仕事もたくさんある)。パーシグが説いた哲学は、単なるバイク修理の枠を超え、現代社会の根本的な課題(品質と効率、そのバランスをどう取るべきか)を鋭く問いかけています。
いや、わろてるけど他人事じゃないでしょ。現在の「AI活用≒効率化・生産性向上」を当たり前としたビジネス慣習がこのような事態を促したのであり、事の大小はあれど、この環境下を生きる誰もが直面していてもおかしくはない事態。
この騒動を目にして、ふと本書を思い出しました。この本は単なるバイク好きによるバイク好きのためのオートバイの修理技術を説くものではありません。専門家に委ねるのではなく、自らの手で機械に向き合うことを通して、物事の本質や「クオリティ(広義の品質)」とは何かを探求する哲学書(フィクション化された自伝)です。現代はAI(専門家の代替)やデジタルツールで効率化を謳いますが、JALの騒動は、その陰で本来不可欠な「気配り」が失われている現実を突きつけ、パーシグが説いた「急ぐ」ことの対極にある「入念に、慎重に解き明かす」という姿勢は、生産性至上主義に対する痛烈な批判として響きます。
AIの万能感に酔いしれ、一つのことに深く向き合わず、次々と別の作業に手を出す「マルチタスク中毒」とも言える現代の病。この病が原因で、私たちは品質に徹底的に向き合うための余白を失っているのではないでしょうか(もちろん品質をそこまで気にしなくてもいい仕事もたくさんある)。パーシグが説いた哲学は、単なるバイク修理の枠を超え、現代社会の根本的な課題(品質と効率、そのバランスをどう取るべきか)を鋭く問いかけています。
『実務論点 ブロックチェーンの法務:暗号資産と電子決済手段』
- 書籍: 実務論点 ブロックチェーンの法務:暗号資産と電子決済手段
- 推薦者: 水塚紗雪
ウォレット、Defi、ステーキングやレンディング、暗号資産ファンド、ステーブルコイン等の最もトレンドな領域で必要な論点を分かりやすく体系的にまとめてくださっている著書。
特筆すべきは痒いところに手が届く「網羅性」で、基礎的な面から未解決の論点まで幅広く学ぶことが可能です。
恥ずかしながら分かっていたようで、全く理解していなかった点を多く学ばせて頂きました。
暗号資産を活用したビジネスを検討する起業家、法務担当者はもちろんのこと、新規事業担当者にも必ずインプットして頂きたい本です。
特筆すべきは痒いところに手が届く「網羅性」で、基礎的な面から未解決の論点まで幅広く学ぶことが可能です。
恥ずかしながら分かっていたようで、全く理解していなかった点を多く学ばせて頂きました。
暗号資産を活用したビジネスを検討する起業家、法務担当者はもちろんのこと、新規事業担当者にも必ずインプットして頂きたい本です。
4.長期視点で未来を読むノンフィクション/SF/思想書
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
- 書籍: プロジェクト・ヘイル・メアリー
- 推薦者: Hiroki Morita
YoutTubeやNetflixのオススメがなんか微妙で、全く新しい刺激が、もっと別のエンタメが欲しいという方、海外SF小説はいかがでしょうか?
ネタバレになるので内容ほとんど言えませんが、読みやすい文体で、展開も早いので、止まらず読めますのでご安心ください。
2021年出版ですが、映画製作も進行中で、現在も話題の小説です。
ネタバレになるので内容ほとんど言えませんが、読みやすい文体で、展開も早いので、止まらず読めますのでご安心ください。
2021年出版ですが、映画製作も進行中で、現在も話題の小説です。
『故郷/阿Q正伝』
- 書籍: 『故郷/阿Q正伝』
- 推薦者: ぷんやりなエンジニア
負けても「勝った」と思い込めるのは、幸せか?それとも悲劇か?『阿Q正伝』は、清末中国の一人の男を通して、自己欺瞞と集団心理の怖さを笑いと皮肉で描きます。
同じく収録された『狂人日記』では、狂人の視点から権威や制度の暴力性が暴き、現代にも通ずる普遍的な構造を批判する切れ味があります。
そして最後に『故郷』は、時代の変化と人の変化を静かに映し出し、読後しばらくの清涼感が得られます。
半日もあれば読める短編3本。古典でありながら、現代批判とも未来予測とも捉えることができる名作です。
同じく収録された『狂人日記』では、狂人の視点から権威や制度の暴力性が暴き、現代にも通ずる普遍的な構造を批判する切れ味があります。
そして最後に『故郷』は、時代の変化と人の変化を静かに映し出し、読後しばらくの清涼感が得られます。
半日もあれば読める短編3本。古典でありながら、現代批判とも未来予測とも捉えることができる名作です。
5.物語と現代社会
スーパースターを唄って。
- 書籍: スーパースターを唄って。
- 推薦者: Lawrence
重すぎる現実描写に、日本が舞台であることを忘れてしまうほど。どん底の環境でも、ひたむきに生きる少年と音楽への情熱が、胸を強く揺さぶる人間ドラマ。音楽好きな人、特にライブハウスに行ったことがある人におすすめです。
『人間たちの話 』
- 書籍: 人間たちの話
- 推薦者: masao i
「SFは難解そう…」と感じる人にこそ読んでほしい短編集です。星新一を彷彿とさせるユーモアと軽妙な語り口が魅力で、ショートショートほど短くはありませんが、どの作品も手軽に読めます。緻密なロジックを追求するのではなく、ユニークな設定から生まれる人間たちの滑稽さや愛らしさを、軽やかに描き出しています。休暇は、現実から飛躍するためにある。だからこそ、ロジックよりもゆるさを大事にしたい。そんな気分にぴったりの、突拍子もない物語に浸る贅沢を、ぜひ味わってほしい一冊です。地球名物ラーメンを軸に宇宙人との交流を描く「宇宙ラーメン重油味」や、ジョージ・オーウェルの『1984年』を思わせる奇妙な監視社会の日常を描く「たのしい超監視社会」など、タイトルだけでも心惹かれる物語が満載です。
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。