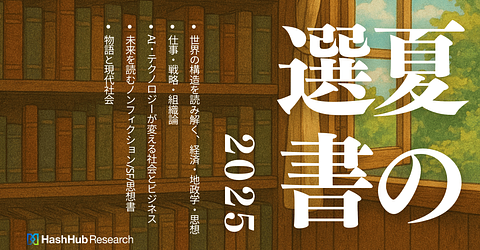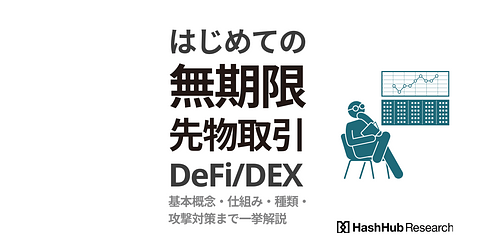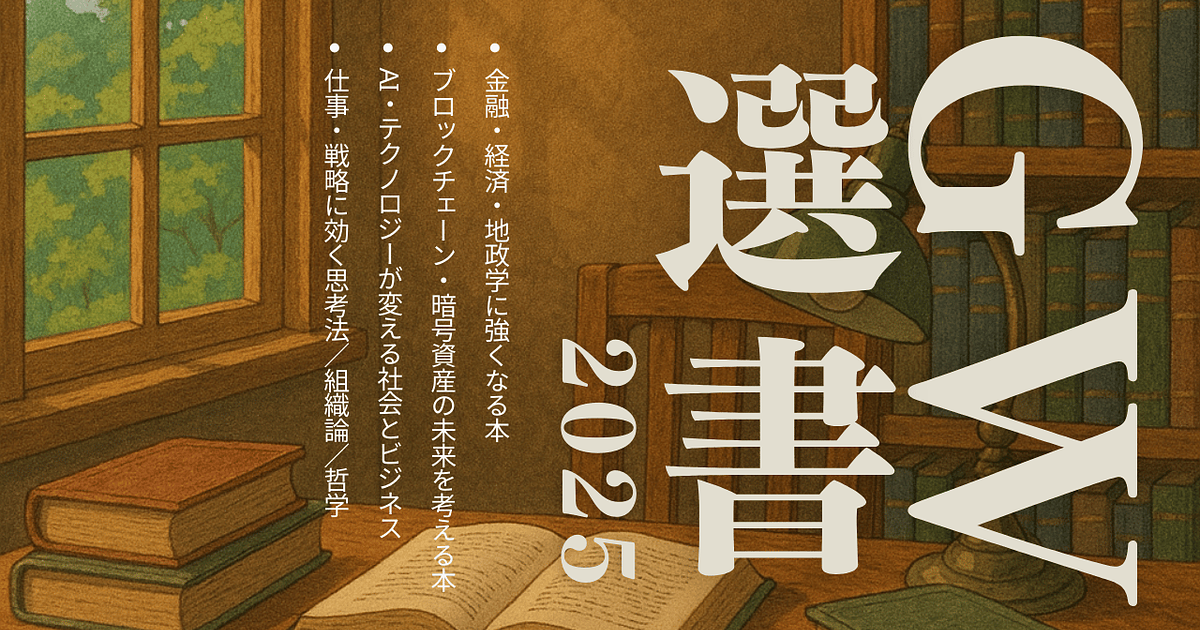
【2025年GW選書】HashHubチームが選ぶ、知的好奇心を刺激する推薦図書
2025年05月02日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 1.金融・経済・地政学に強くなる本
- 『世界恐慌とブロック経済』
- 『世界秩序の変化に対処するための原則 なぜ国家は興亡するのか』
- 『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書)
- 『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』
- 『Mr. Market Miscalculates』—ミスターマーケットの誤算
- 2.ブロックチェーン・暗号資産の未来を考える本
- 『The Unaccountability Machine』― 新金融時代の「システムリスク」を根源から問う
- 『芸術起業論』村上 隆 (著)
- 『推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』中山 淳雄 (著)
- 3.AI・テクノロジーが変える社会とビジネス
- 『人類を変えた7つの発明史 火からAIまで技術革新と歩んだホモ・サピエンスの20万年』
- 『メタトレンド投資 10倍株・100倍株の見つけ方』 中島聡 (著)
- 『THE SCALING ERA: AN ORAL HISTORY OF Al, 2019-2025』— 私たちはAGIを作るのか? その先に何が待つのか?
- 4.仕事・戦略に効く思考法/組織論/哲学
- 『失敗の本質』
- BATNA――交渉のプロだけが知っている「奥の手」の作り方
- 『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』 (講談社現代新書)
- 『歩く マジで人生が変わる習慣』池田光史 (著)
- 『お金の減らし方』森 博嗣 (著)
- 『流れをつかむ技術』桜井章一 (著)
- 『The Art of Attack』—攻撃者の視点から学ぶ、実践的サイバー防御術
- 『The case against conversational interfaces』—人とAIが“無言でバターを渡す”ように働く日
ゴールデンウィークは、日々の喧騒を離れ、自分自身と向き合いながら知的好奇心を深める、またとない時間です。情報に溢れる現代だからこそ、このような“静の時間”は、視野を広げ、思考を深める貴重な機会となります。
HashHubでは、継続的な学びと多角的な視点の重要性を重視しています。今回その一環として、ゴールデンウィークに「これから読みたいもの」や「最近読んでよかったもの」をチームメンバーに尋ねたところ、それぞれの関心や思考を反映した多彩な推薦が寄せられました。
この特集では、チームから寄せられた推薦図書(web記事含む)をまとめ、社外の読者ともその知見を共有します。多様な選択肢の中から関心のある分野を見つけやすいよう、テーマ別に分類して紹介しています。Web3の未来、世界経済の複雑さ、AIの影響、あるいは私たちの世界を形作る深層構造に関心がある方にとって、きっと興味深い一冊が見つかるはずです。
1.金融・経済・地政学に強くなる本
『世界恐慌とブロック経済』
- 書籍: 『世界恐慌とブロック経済』
- 推薦者: Junya Hirano
今まさに貿易戦争で、世界がブロック経済化しようとしています。本書籍は、1929年に発生した世界恐慌下、危機に対応するため各国が実施したブロック経済について当時を分析します。ブロック経済にはどのような効果があったのか、第二次世界大戦へつながるブロック経済の実態について、現代経済分析ほど様々な数値が用意できないという制約がある中で示唆的な内容を提供しています。
『世界秩序の変化に対処するための原則 なぜ国家は興亡するのか』
- 書籍: 『世界秩序の変化に対処するための原則 なぜ国家は興亡するのか』
- 推薦者: Junya Hirano
レイ・ダリオ氏著作の当書籍は過去にHashHubリサーチでも推薦しているので、読んだことがある方も多いと思いますが、それを踏まえて再度推薦します。それは今のアメリカと国際政治の基礎背景を知るのに、これほど適した書籍はないからです。貿易戦争は過程や手段でしかなく、覇権国としてのソフトランディングが今アメリカが目指すところであり、背景知識が変わります。
『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書)
- 書籍: 『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書)
- 推薦者: 構成を考えすぎるエンジニア
甘い砂糖の背後には、奴隷制・帝国主義・交易という重たい構造があります。かつて砂糖は、ものの価値をめぐるグローバルな流通ネットワークの中心にありました。その姿は、今のトークンやNFTを取り巻く現状ともどこか重なります。価値はどのように生まれ、どう流れ、どう消費されるのか。歴史は繰り返す。ただし、形を変えて。「構成とは思想である」—そんな問いを持つ休日に、ぜひ。
『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』
- 書籍: 父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。
- 推薦者: masao i
時間が経っても色あせず、ふと思い出して読み返したくなるような、学びの多い一冊です。(翻訳版は2019年刊行)
この本は、元ギリシャ財務大臣の著者が10代の娘に語りかける形で、経済の本質をわかりやすく伝えてくれます。「資本」などの難しい言葉をあまり使わずに、格差の始まりや市場経済の仕組み、金融の裏側、さらには暗号資産や環境の話まで、現代社会(と未来を見据える)に欠かせないテーマをしっかりカバーしています。
古代ギリシャ神話から今のテクノロジーまで、豊富なたとえ話が随所に盛り込まれていて、読みやすく、それでいて読み返すたびに新しい発見があります。どうしてお金や富が一部の人に集中するのか(それは問題の本質なのか)、なぜ経済危機は何度も起きるのか――そんな疑問にも丁寧に向き合ってくれて、複雑な世界を読み解くヒントが得られるはずです。
もしこのようなテーマに興味があっても「活字はちょっと苦手…」という方には、昨年や一昨年に話題になった『きみのお金は誰のため』や『13歳からの地政学』もおすすめです。どちらも平易な文章でスラスラ読める一方で、お金の本質や格差、国際関係や組織構造といった重要なテーマについて、考えるための視点や基礎的な理解を与えてくれる一冊です。読みやすさと学びのバランスがちょうどよく、読書にあまり慣れていない方にもおすすめです
『Mr. Market Miscalculates』—ミスターマーケットの誤算
- webエッセイ: Mr. Market Miscalculates
- 推薦者: masao i
喧噪やまぬ市場予測や、次々と現れる「専門家」たちの声に、つい心が揺れてしまう…そんなご経験はありませんか? 日々の値動きに一喜一憂しがちな私たちに、著名投資家ハワード・マークス氏のメモ「Mr. Market Miscalculates」は、一度立ち止まって市場の本質を見つめることの重要性を教えてくれます。
マークス氏は、2024年夏の市場急変といった具体的なケーススタディを用いながら、市場がいかに感情に左右されているか――まさにベンジャミン・グレアムが描いた「ミスター・マーケット」の気まぐれさ――を、彼独特のユーモアと示唆に富む風刺画を交えて鮮やかに描き出します。
市場の価格形成は、常に緻密で合理的な計算に基づいているわけではなく、むしろ集団心理、時にはパニックに近い感情によって大きく突き動かされるのだと、本質を突くのです。マークス氏が鋭く指摘するように、まさに「危機に際しては全ての相関が1になる」かのごとく、良い資産も悪い資産も一緒くたに売り叩かれてしまう。また、「同じ情報でも市場のムード次第で解釈が大きく揺れる」といった、市場でしばしば見られる光景の裏にある心理的なメカニズムを、分かりやすく解き明かしてくれます。(こうした市場心理の根底にある、私たち自身の「自己欺瞞」とも言えるメカニズムに更に興味を持たれた方は、『人が自分をだます理由/The Elephant in the Brain』も示唆に富むかもしれません。)
だからこそ、「確実な予測」や「絶対的なシナリオ」といった単純化された言説には、一歩引いて向き合う必要があるのでしょう。マークス氏の洞察に触れることで、感情が渦巻く市場の波にただ翻弄されるのではなく、その動きを冷静に観察し、本質的な価値を見極めることの大切さが、深く腑に落ちるはずです。気まぐれに見える市場と、より建設的に、そして知的に向き合うための基本的な視座を与えてくれる一編と言えるでしょう。
2.ブロックチェーン・暗号資産の未来を考える本
『The Unaccountability Machine』― 新金融時代の「システムリスク」を根源から問う
- 書籍: 『The Unaccountability Machine:Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind』Dan Davies 著
- 推薦者: masao i
USDCのようなステーブルコインが決済を変え、伝統的な金融資産がトークン化されスマートコントラクトで動く未来。ブロックチェーンと金融の融合は、間違いなく大きな利便性と効率性をもたらします。しかし、私たちはその裏に潜むリスクを十分に理解しているでしょうか? DeFiの歴史は、ハッキングや市場の混乱を通じて、その一端を既に私たちに教えてくれています。
しかし、本書『The Unaccountability Machine』が示唆するのは、問題は単なる技術的バグや市場の予測ミスに留まらない、ということです。本書は特定の技術について書かれたものではありませんが、複雑な「システム」――特に人間がそれを設計し、運用し、相互作用する際に必然的に生じる――固有の構造的課題、「説明責任の欠如」や予期せぬ連鎖反応のメカニズムを、歴史的な事例を通して深く掘り下げます。
ステーブルコインの準備金管理、クロスチェーンブリッジの脆弱性、トークン化資産の法的整理…。これら最先端の課題を考えるとき、DeFiの教訓はもちろん重要です。しかし本書は、それらの根底に流れる、より普遍的で人間的な、つまり「システムを扱う人間の限界」からくるリスク――複雑性のブラックボックス化、責任所在の曖昧化、インセンティブ設計の意図せぬ帰結――に目を向けさせます。
本書が提供する歴史的・構造的な視点は、新しい金融システムの開発者、リスク評価に関わる投資家や規制当局者の方々はもちろんのこと、複雑化する自社の業務プロセスや組織運営における「見えにくいリスク」や「責任所在の曖昧さ」に関心を寄せる企業の管理職の方々にとっても、示唆に富む内容です。技術的な議論を超え、あらゆるシステムに潜む本質的な「死角」を理解し、より安全で持続可能な未来を築きたいと願うすべての人にとって、重要な気づきを与えてくれる一冊となるでしょう。
『芸術起業論』村上 隆 (著)
- 書籍: 『芸術起業論』村上 隆 (著)
- 推薦者: でりおてんちょー
村上隆さんの『芸術起業論』は、アーティストという立場から「作品=商品」「世界観=ブランド」と割り切り、起業してルイ・ヴィトンとコラボしたり、まず海外オークションで実績を叩き出してから日本へ逆輸入するまでのビジネス戦略を赤裸々に語った本です。個人的な読みどころは、「良いものを作るだけでは誰にも届かない」「販路とPRを自分で握れ」というメッセージで、国内評価に行き詰まっているクリエイターやスタートアップが読めば、先にグローバルで結果を作ってから国内を攻め直すという発想が腑に落ち、参考になります。さらに村上さんは、自身でもNFTコレクション〈Murakami.Flowers〉を運営しており、ジェネラティブアートNFTのミントやリアル展示、グッズ販売をワンセットで回す設計が、本書で語られる「市場ごと作る思考」をそのままweb3に移植したもののように個人的には感じました。中長期で愛されるプロジェクト設計に悩むNFT事業者にこそ、ページをめくるたびに即戦力のヒントが得られるのではないでしょうか。
『推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』中山 淳雄 (著)
- 書籍: 『推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』中山 淳雄 (著)
- 推薦者: でりおてんちょー
最近の国内web3業界では、推し活やファンダムの仕組みづくりが語られる機会が増えてきていると個人的に感じているのですが、そのあたりの解像度を高める入門記事として一番役に立ったのが、中山淳雄さんの本です。本書の肝は、推しはただの顧客ではなく、拡散・二次創作・クラファンまで引き受ける共犯者だということで、このあたりは個人的に好きだったCC0 NFTムーブメントや、Lootのようなボトムアップ型NFTプロジェクトとも通じるところがあると思っています。現在、韓国アイドルからVtuberまでもがweb3に参入する事例が相次いでいますが、こうしたことを踏まえると「トークン設計よりファン設計が先」というインサイトは大事になってきますし、コミュニティが自走し始めるとマーケティング等の費用が激減したり収益が安定するといったロジックは、web3事業者にも参考になる内容になっているはずです。
3.AI・テクノロジーが変える社会とビジネス
『人類を変えた7つの発明史 火からAIまで技術革新と歩んだホモ・サピエンスの20万年』
- 書籍: 『人類を変えた7つの発明史 火からAIまで技術革新と歩んだホモ・サピエンスの20万年』
- 推薦者: Junya Hirano
火や文字、活版印刷や科学、鉄道、コンピュータなどの発明がどういったもので、それらが後の時代にどう影響したのかも丁寧に説明されているので、長い歴史を俯瞰できます。現在のAIの進化は、私たちの仕事の仕方は勿論、後に行動規範・教育・文化、あるいは社会通念にも影響を与えることが明白です。その結果は未来の住人しか知りえませんが、その想像力や未来予測に、本書は少しばかりの貢献をするかもしれません。
『メタトレンド投資 10倍株・100倍株の見つけ方』 中島聡 (著)
- 書籍: 『メタトレンド投資 10倍株・100倍株の見つけ方』 中島聡 (著)
- 推薦者: Lawrence
短期的な市場のノイズに惑わされず、長期的な視点で社会やテクノロジーの大きな変化(メタトレンド)を捉え、将来有望な企業(投資先)を見つけ出す投資アプローチを紹介しています。暗号資産やWeb3分野にも応用できる考え方が多く、これからの未来を見通す上で示唆に富む一冊です。著者が保有している銘柄と保有理由を知ることができる特典もついてました。
著者は、ファンダメンタル分析はあくまで過去・現在の数値に基づくもので将来の成長性を必ずしも踏まえられていない、テクニカル分析は占いと大差ない、と断言してます。これらの主張がさっぱりとした意見で、全体的に分かりやすくすぐ読めてしまう書籍でした。
どのようにメタトレンドを認識するか、どういう手法で投資をするか、著者自身の主要な情報源は何か、どういう解釈の仕方をするかなどを具体的に解説しているので参考になります。
ちなみに、著者はブロックチェーンはメタトレンドにはならないと考えているようです。この点は私と意見が異なりますが、そういうスタンスのオピニオンを理解することも学びとなりました。
『THE SCALING ERA: AN ORAL HISTORY OF Al, 2019-2025』— 私たちはAGIを作るのか? その先に何が待つのか?
- 書籍: 『THE SCALING ERA: AN ORAL HISTORY OF Al, 2019-2025』Dwarkesh Patel著
- 推薦者: masao i
『THE SCALING ERA: AN ORAL HISTORY OF AI, 2019–2025』は、AIが飛躍的な進化を遂げた「スケーリング時代」の記録を、ポッドキャスターのDwarkesh Patel氏が、最前線のAI研究者や思想家たちへのインタビューを通じて編み上げたオーラル・ヒストリーです。
本書を通じて著者が読者に提示するのは、AGI(汎用人工知能)の実現をめぐる四つの核心的な問い——「私たちは本当にAGIを作るのか(作れるのか)?」「もし作るとしたら、どのように?」「作ったことを後悔することになるのか?」「そして、その後に何が起こるのか?」。これらは技術・倫理・社会の境界を越えて交差する、本質的かつ未解決の問いであり、本書はその答えを一方的に示すのではなく、進行中の歴史の証言を通じて、読者自身に思考を委ねます。
AGIの登場を「スケーリング仮説」に基づいて楽観視する立場、AI研究の自動化が引き起こす軍事的リスクを警告するLeopold Aschenbrenner氏、より緩やかな進化を見通すTyler Cowen氏、人間の内面と意味を問い直すIlya Sutskever氏、自動化の速度とそれに伴う社会的リスクを指摘するAjeya Cotra氏など、多様な視点を持つ論者たちが本書の中で活発な議論を交わしています。さらに、「解釈可能性」や「アライメント(例:AIが自己目的化して暴走するのをどう防ぐか?)」といった技術的な課題から、計算資源・電力といったインフラの制約、知能爆発の可能性に至るまで、AI開発を取り巻く現在進行形の論点が多角的に取り上げられています。
本書は、そうした複雑な問題群に対し、漠然とした不安や無邪気な期待も含めて、AIの未来に向き合うための視座と考察の起点を提供するものです。技術的なディテールと根源的な問いを行き来しながら、AIの行方を捉えたい読者にとって、この一冊は最適なガイドとなるでしょう。なお、AGI研究の現在に関心のある方には、著者が発信するポッドキャストおよびブログ「Dwarkesh Podcast」も併せておすすめです。
4.仕事・戦略に効く思考法/組織論/哲学
『失敗の本質』
- 書籍: 『失敗の本質』戸部良一、 鎌田伸一、 村井友秀、 寺本義也、 杉之尾宜生、 野中郁次郎著
- 推薦者: 加藤 諒
本年初に野中郁次郎先生がご逝去され、先生の代表的な著作である本書を改めて読みなおしました。
本書は、太平洋戦争の各戦線で日本軍が敗北を喫した要因を分析し、ビジネスや組織運営にも活かせる「失敗の本質」を研究した本です。
「成功の秘訣」は100人100通りなのかもしれませんが、「失敗の本質」は戦力の分散や逐次投入、戦略目的が多義的で曖昧であること、短期決戦志向等
いくつかに集約されますし、多くの人が同じ轍を踏む傾向にありますので、予め本書を読んでおくことにより、失敗を回避できる蓋然性が上がるのではないでしょうか。
BATNA――交渉のプロだけが知っている「奥の手」の作り方
- 書籍: BATNA――交渉のプロだけが知っている「奥の手」の作り方 齋藤孝/射手矢好雄著
- 推薦者: 加藤 諒
推薦者は、ノースウエスタン大学院に留学中にNegotiationのクラスを履修して以来、日本の義務教育でも交渉学/交渉術を「必修科目」とすべきだと考えています。
交渉の概念や方法論を正しく学べば、ビジネスはもちろん、プライベートも円滑にまわるようになり、人生が豊かになります。
交渉学の教科書としては、"Getting to Yes"が「ハーバード流交渉術」として広く知られるところですが、一般向けとしては若干難易度が高いこともあり、はじめて交渉の概念に触れる方には、本書を強くお薦め致します。
本書のタイトルにもなっているBATNAとは、Best Alternative to Negotiated Agreementの略語で、「交渉が決裂した場合に、取りうる選択肢のうち最良のもの(最良の代替案)」のことです。交渉の準備段階からBATNAをきちんと用意しておくことで、戦略的に、余裕をもって交渉を進めることが出来ます。
著者は、「声に出して読みたい日本語」で著名な齋藤孝先生と、弁護士として長年国際ビジネス交渉にあたられている射手矢好雄先生で、説得力があり、かつわかりやすい良書です。
『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』 (講談社現代新書)
- 書籍: 『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』 (講談社現代新書)
- 推薦者: 構成の中で溺れたエンジニア
「ストーリー」ではなく「データベース」を消費する。かつて物語が担ってきた"欲望の構造"は今や萌え(当時は流行しました)や記号に集約されてしまい、それらのデータベースからの組み替えで新たな『擬似作品』が作られるようになりました。この本はそんな現代の"動物化"した消費社会を冷静に描いた一冊。その姿はDAOやNFTのような分散型カルチャーとどこか重なります。Web3を巡る"好き"や"推し"が、どんな構造に支えれているのか。ちょっとだけ立ち止まって考えてみたくなる休日に、ぜひ。
『歩く マジで人生が変わる習慣』池田光史 (著)
- 書籍: 『歩く マジで人生が変わる習慣』池田光史 (著)
- 推薦者: Lawrence
2025年2月発売。このGWに読もうとしている一冊です。ウォーキングを単なるエクササイズではなく、脳や身体、生産性、創造性を高め、現代人の問題を解決する鍵として捉え直す視点に興味を持ちました。
最新の研究や偉人の習慣を交え、「座りっぱなしの害はタバコ並」「歩きやすい街がGDPを生む」といった具体的なデータや、現代の靴が身体性を阻害しているという「不都合な真実」にも言及しているとのこと。日常的な「歩く」という行為から、幸福論や文明論にまで繋がる壮大なテーマに惹かれています。ただ、正直風呂敷を広げ過ぎでは?という疑問もあります…。この連休でじっくり読み込んで確かめてみたいです
『お金の減らし方』森 博嗣 (著)
- 書籍: 『お金の減らし方』森 博嗣 (著)
- 推薦者: でりおてんちょー
web3の世界では、「価格が◯◯ドルを超えた」「トークン時価総額××億」のように、派手なお金の数字が取り沙汰されがちですが、森博嗣さんの『お金の減らし方』という本は、そうしたマネーゲームをいったん横に置いて「そもそも自分は何にワクワクし、どんな体験にお金を払いたいのか?」を問い直させてくれる一冊です。著者は印税長者なのに、研究施設づくりや鉄道模型など子どもの頃の夢にしかお金を使わないそうです。そして、余計な支出をそぎ落とした結果、必要な金額もストレスも激減し、むしろ自由度が上がったと語っています。見栄消費や「お金がないからできない」という言い訳をサラッと切り捨てるところが個人的に印象深く、読んでいるうちに財布より心が軽くなる感覚がありました。個人的には、本書に書かれている「数字は他人が貼った値札にすぎない」「お金を減らすことは人生を設計し直すこと」といった視点を持てれば、プロジェクトのKPIやバリュエーションも手段として冷静に捉え直せますし、デジタル空間でモノを売る際のインサイトが得られると思います。GWののんびりした機会に数字を追うレースから少し離れ、本当に欲しい価値リストを書き出してみるのも良いのではないでしょうか。
『流れをつかむ技術』桜井章一 (著)
- 書籍: 『流れをつかむ技術』桜井章一 (著)
- 推薦者: でりおてんちょー
先に申し上げておくと、本書は個人的に人生のバイブルとしている一冊です。サイバーエージェント代表取締役社長である藤田 晋さんの師匠の一人であり、麻雀界で20年無敗を誇った桜井章一さんという方が著者で、「勝ちに行くより、流れに乗るほうが早い」といったのような微細な感覚の磨き方を教えてくれる内容となっています。ポイントはとにかく「力を抜く」ことで、場の空気や人の感情、ちょっとした運気の揺れをキャッチするには、がむしゃらよりもリラックスの方が効きが良いことを気づかせてくれます。詳細はぜひ本書を手に取っていただきたいのですが、要はうまく流れに乗ったらスッと進み、悪い流れならサッと身を引く、その判断を身体で覚えよう、という話がテンポよく語られた一冊で、麻雀を知らない方も勝負の世界に身を置いているのであれば何か必ず一つはインサイトを得られる本だと思います。ちなみに、同著者の『感情を整える ここ一番で負けない心の磨き方』という本もおすすめなので、お時間ある方はぜひ調べてみてください
『The Art of Attack』—攻撃者の視点から学ぶ、実践的サイバー防御術
- 書籍:The Art of Attack
- 推薦者: masao i
『The Art of Attack』が解き明かす「攻撃者マインドセット(AMs)」は、現代の情報セキュリティを理解する上で不可欠な鍵です。本書は、攻撃者が目的達成のためにどう思考し、行動するかを具体的に描き出します。例えば、SNSの何気ない投稿から物理的な侵入経路やタイミングを探り、企業の求人情報から使用しているソフトウェアやシステムの脆弱性を推測する。彼らは最終目標から逆算して計画を立て、状況に応じた巧妙な「プリテキスト(偽装理由)」を作り上げ、一見無関係に見える情報を繋ぎ合わせ、武器へと変えるのです。
個人にとって、これは遠い世界の出来事ではありません。日々届く巧妙なフィッシングメールは、過去のデータ侵害情報や公開されているあなたのプロフィールからパーソナライズされ、「確証バイアス」(自分に都合の良い情報だけ信じる傾向)や「楽観主義バイアス」(自分は大丈夫だろうと思う傾向)といった心理的な隙を巧みに突いてきます。電話口での丁寧な言葉遣いや共感を装う態度(ビッシングにおけるラポール形成)に警戒心が薄れ、つい重要な情報を漏らしてしまう危険性も、本書は具体例と共に警鐘を鳴らします。AMsを学ぶことは、こうした手口の構造を理解し、日常に潜むリスクを見抜くための実践的な訓練となるでしょう。
組織においては、最新のファイアウォールを導入するだけでは不十分です。従業員一人ひとりがAMsの視点を持ち、例えば「なぜ安易に見知らぬUSBメモリをPCに挿してはいけないのか」を、攻撃者の初期侵入経路確保という具体的な文脈で理解することが極めて重要になります。本書で提唱される、現実的な脅威をシミュレートするレッドチームによる実践的なテストの重要性や、インシデント経験から学び組織をより強靭にする「アンチフラジリティ」の考え方は、形骸化しやすいセキュリティポリシーや研修を見直し、実効性のある防御体制を築く上で欠かせない視点を提供します。
AMsを学ぶことは、単なる知識習得に留まらず、脅威に対する解像度を格段に高め、より効果的で本質的な防御を可能にする「思考のOS」を手に入れるようなものです。なお、『The Art of Attack』が個々の攻撃者の思考と戦術(ミクロ)に焦点を当てる一方、先に推薦した『The Unaccountability Machine』は、複雑なシステム自体が必然的に抱える構造的リスクや説明責任の欠如(マクロ)という異なる角度から問題を考察します。両書を併読することで、現代社会における脅威とリスクに対し、より複層的で深い洞察を得られるはずです。
『The case against conversational interfaces』—人とAIが“無言でバターを渡す”ように働く日
- エッセイ(web記事): The case against conversational interfaces
- 推薦者: masao i
「対話型UI(≒自然言語処理)がAI時代の主流になる?」という期待に対し、このエッセイはまず、「いや、PC作業においては今なお従来のインターフェースの方が実用的でしょ」と、データ効率の観点から冷静に指摘します。現場感覚とテクノロジーへの期待(SNSでの過度な煽り)のズレを突きつける、見過ごされがちな現実的な論点です。
しかし、このエッセイが真に問題提起しているのは、「AI vs 人間」といったゼロサム的な発想そのものです。AIは“代替”ではなく“補完”の存在として捉えるべきであり、その進歩がもたらすのは、何かを「奪う」ことではなく、「まったく新しい可能性の解放」なのだと。
既存のツールやインターフェースとAIが有機的に連携し、人間の知的活動をより滑らかに、自然に拡張していく——それは、例えるなら長年連れ添った朝食の食卓で、無言でバターを渡し合うような、心地よい協調の未来です。
「AIは敵か味方か」といった単純な構図を超えて、より創造的で実践的な協働のモデルを考えたいビジネスパーソンにとって、このエッセイは連休中に読むにふさわしい、静かで示唆に富んだ一編です。
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。