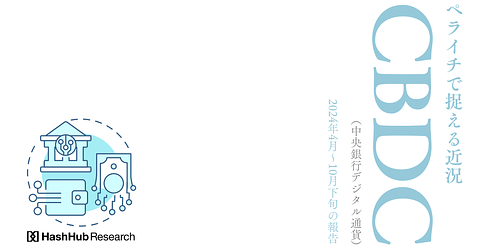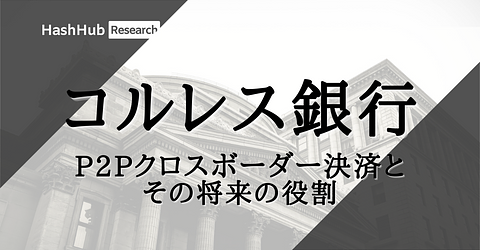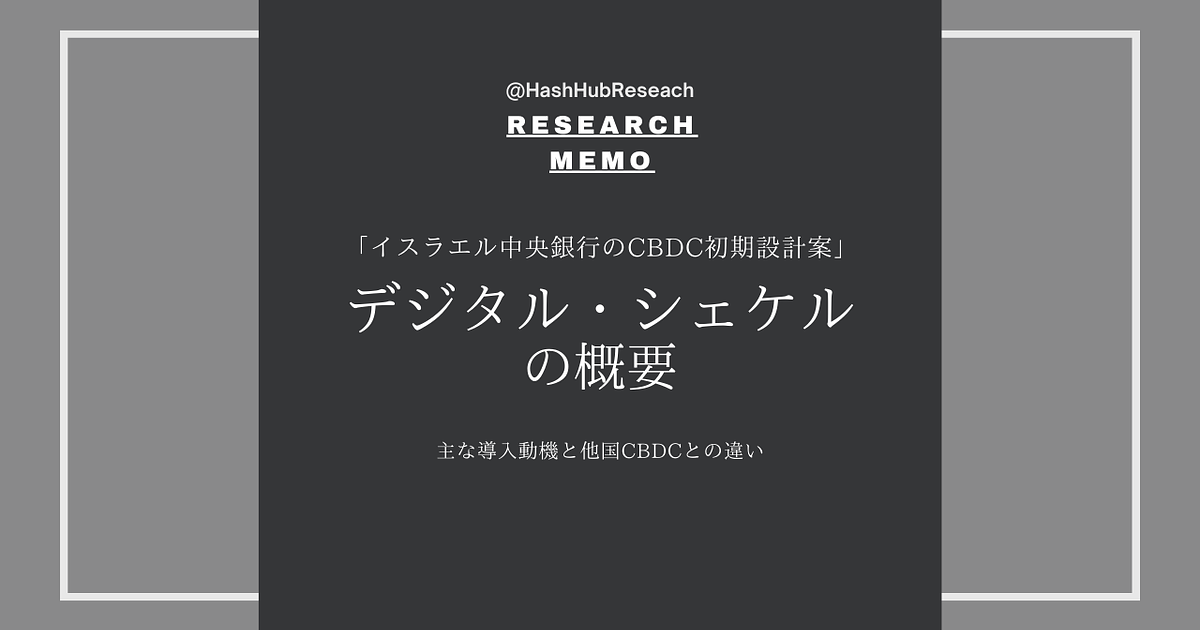
イスラエル中央銀行の「デジタル・シェケル」CBDC初期設計案の概要|主な導入動機と他国CBDCとの違い
2025年03月06日
リサーチメモ(masao i)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
2025年3月、2017年ごろからCBDC(中央銀行デジタル通貨)導入を検討し続けてきたイスラエル銀行がリテールとホールセールの両方の目的に用いられる「多目的CBDC」を謳ったデジタルシュケル(DS)の初期設計文書を公開。そのページ数なんと136ページ。
ということで、その要点だけを掴む目的でデジタルシュケル(DS)の初期設計文書を参考にその導入動機と他のCBDCとの主な違いについての基礎調査をAIを活用して実施しました。以下、その結果を共有致します。
なお、イスラエル銀行は以前から「欧州がCBDCを導入するのであれば」との条件付きで開発を進める方針を示しており、本稿執筆時点においても技術仕様を考慮しないハイレベルな構想段階の発表にとどまっています。仮に開発が進められる場合でも、技術仕様の検討、規制整備の変更等々を伴う可能性が高く、その実現には相応の時間を要すると考えられます。あくまで構想段階である点をご留意ください。
参考資料:デジタルシュケル(DS)の初期設計案
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >