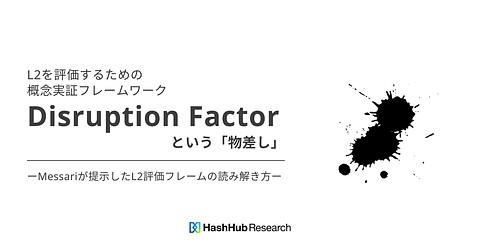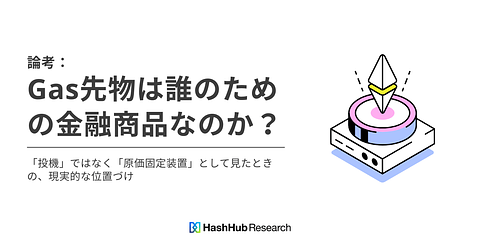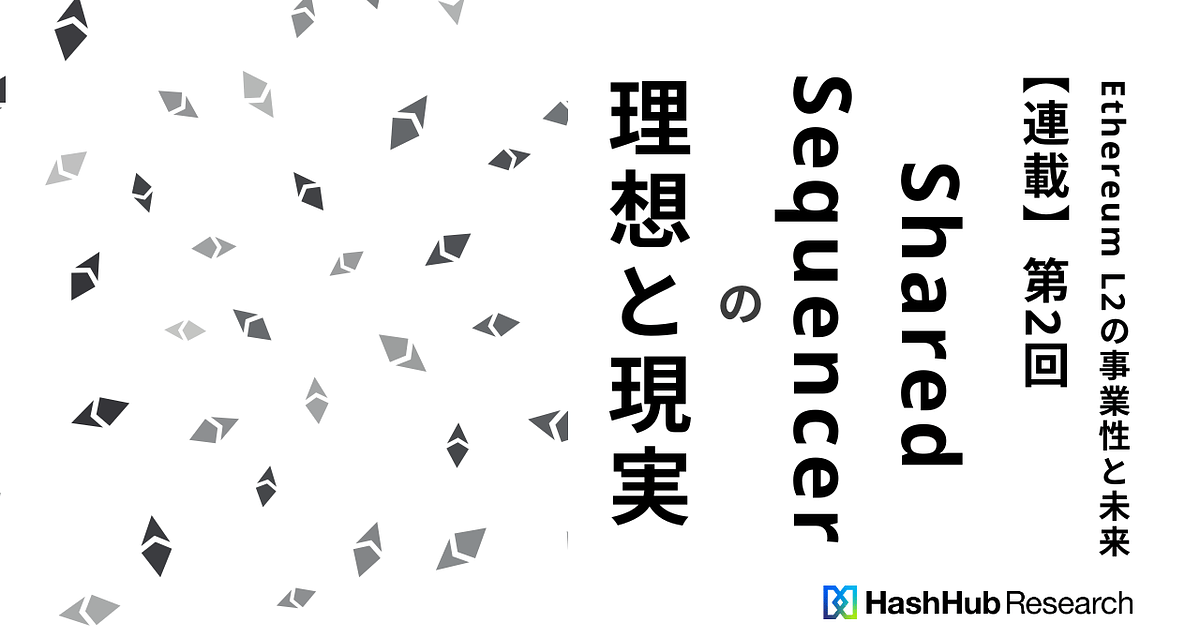
連載:Ethereum L2の事業性と未来|第2回|Shared Sequencerの理想と現実
2025年09月03日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
連載のはじめに
前回は「L2はどこで稼いでいるのか?」を整理しました。結論として、BLOB(EIP-4844)後は手数料収益が圧縮され、Sequencer収益(Priority Fee/MEV)が命綱になりつつあります。
ただし、この「Sequencer独占モデル」が永続するとは限りません。次のステージとして議論が進むのが、分散型シーケンサーです。本稿では、その中核にある Shared Sequencer を中心に、Decentralized Sequencer(DS) との違いも踏まえて「理想と現実」を解きほぐします。
※脚注・補足例(用語について)
日本語で「分散型シーケンサー」と呼ぶとき、英語では通常 Decentralized Sequencer(略:DS)という表現が使われます。一方で、近年の研究やプロジェクトでは Shared Sequencer を「複数のL2が共通で利用する特定のモデル」として議論することが増えています。そのため英語圏では “Decentralized vs. Shared Sequencer” という対比がよく用いられます。
本連載では混乱を避けるため、以下のように整理して表記しています:
- 分散型シーケンサー(Decentralized Sequencer) … 「1社独占ではなく、複数のノードで取引順序を決める仕組み」全般の総称。
- DS / Decentralized Sequencer(狭義) … 各L2が自前のトークン等を使ってノードを分散させる方式(例:Arbitrum、Starknetが掲げる構想)。
- Shared Sequencer … 複数のL2が共有する共通のSequencerネットワークを使う方式(例:Espresso、Astria、SUAVE、Radius)。
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。