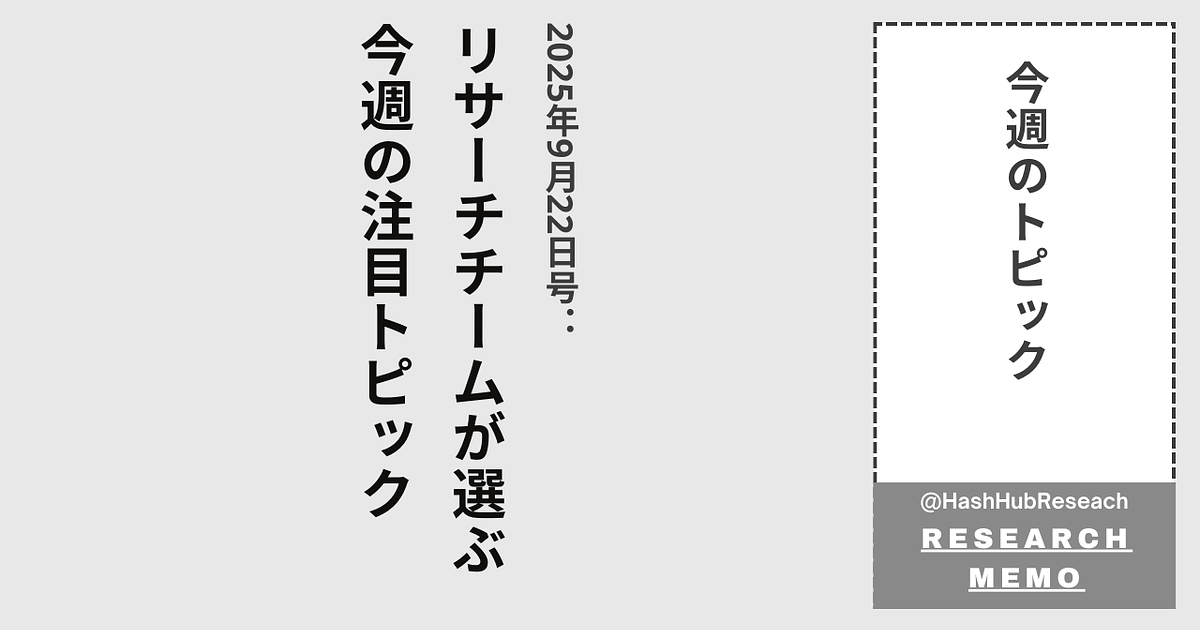
リサーチチームが選ぶ今週の注目トピック 2025年9月22日号
2025年09月22日
リサーチメモ(derio)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 前提
- 今週1週間分のニュースを紹介
- L1トークンの公正価値を測る方法論と事例研究
- RWA市場の機会、課題、そしてBenFenの解決策(by Bixin Ventures)
- Avalanche、エンタープライズ向けブロックチェーン採用を牽引
- Kaito、予測市場から「情報市場」への進化を牽引
- RWAレポート2025 / DUNE
- 暗号資産(Crypto)とロボティクス(Robotics)の交差領域
- 「Pump.fun のライブ配信✖️トークン化モデル」 を、従来型プラットフォーム(TwitchやKick)との比較を交えて解説
- 「予測市場(Prediction Markets)」の技術的な分類とトレードオフ を整理した技術論文風の解説
- 1) 解決(決着)方式:Outcome Resolution
- 2) 流動性モデル:Liquidity
- 3) 市場生成:Event Creation
- 4) マーケット型:Market Types
- 5) 基盤インフラ:Infrastructure
- 全体示唆(トレードオフ)
- 「Pump(pump.fun)のライブ配信 × コイン」が“なぜ稼げる構造になりやすいのか”
- 「予測市場(Prediction Markets)とは何か」
- 新たなマルウェア「ModStealer」とは
- Arc の「USDCガス」仕組みについて
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
前提
本レポートでは、最新のクリプトやWeb3市場、オピニオンに関する記事やスレッドをまとめています。各記事の要点を把握し、トレンドやインサイトを効率的にキャッチアップできる内容となっていますので、ぜひご活用ください。
また、本シリーズは今週1週間分のニュースをまとめたものになります。リアルタイムで情報をキャッチアップしたい方は、「HashHub Research ニュース」をご利用ください。
今週1週間分のニュースを紹介
L1トークンの公正価値を測る方法論と事例研究
The Smart Ape氏は、L1トークンの適正な評価方法を体系的に整理しています。L1は「汎用型」と「アプリ特化型」に分かれ、それぞれ異なる分析フレームワークが必要であると強調しています。
評価の主要ポイント
まず重要なのは「収益」です。ただし、プロトコル全体の収益ではなく、そのうちトークン保有者に還元される収益に注目すべきです。買い戻しやバーン、ホルダーへの分配、開発資金として再投資される場合などが含まれます。対象となる収益が確定したら、年率換算して比較します。
次に使える指標がFDV(Fully Diluted Valuation)/Revenue比率です。伝統的なテック企業では通常8〜15倍程度ですが、L1はこれを大きく上回る傾向があります。
さらに、成長性を測るために以下の指標を確認します。
- アクティブアドレス数
- 取引量
- トランザクション数
- TVL(預かり資産総額)
重要なのは絶対値ではなくトレンドラインであり、継続的に成長しているかどうかが評価に直結します。
また、セキュリティ予算も重要です。理想は手数料収入でネットワークを維持することですが、多くはトークンのインフレに依存します。この健全性はネット発行率(issuance – burn / supply)で確認可能です。
最後にトークンのアンロックが評価を左右します。アンロックの時期と用途が重要で、開発やホルダーへの還元ならポジティブですが、給与やマーケティング目的だとネガティブに働きます。
事例研究
-
Ethereum(ETH)
- 過去1年で約7.4億ドルの収益を生みましたが、EIP-4844による手数料低下が影響しています。この収益はバーンやステーキング報酬に回り、ETH保有者に直接還元されます。FDV/Revenue比率は約675と極めて高いですが、ETHは「価値保存手段」と「世界の決済レイヤー」という特別な地位を持ち、構造的プレミアムが上乗せされています。発行率は0.5〜0.7%と低く、バーンによりデフレになることもあります。
-
Solana(SOL)
- 過去1年で約3.87億ドルの収益を計上し、バーンやステーキング報酬を通じてホルダーに還元されています。FDV/Revenue比率は約370で、ETHより低いですが依然として伝統的企業と比べると高水準です。アクティブアドレス数や取引数の伸びはピークを越えた可能性があり、今後はリテール採用が評価の中心になります。
-
Hyperliquid(HYPE)
- 特徴的なのは収益の100%を買い戻しに充てる点で、すべてがホルダー還元につながります。直近90日で2.55億ドルの収益を上げ、年率換算で約10億ドル。FDV/Revenue比率は約52で、ETHやSOLより現実的な水準です。まだCEX市場シェアは約4.9%にとどまっており、成長余地が大きいと評価されています。
結論
L1トークンの評価は単なる収益だけで決められず、成長性や市場期待が大きな役割を果たします。伝統的な基準で見ると多くのL1は依然として割高ですが、クリプト市場では将来の成長ポテンシャルや投機的期待が価格の主要ドライバーであり続けています。収益やファンダメンタルは基準点にはなるものの、実際の価格形成は「投機と未来志向」で支配されているのが現実です。
RWA市場の機会、課題、そしてBenFenの解決策(by Bixin Ventures)
RWAの歩み
RWAの萌芽は2017〜2018年のSTO試行期にさかのぼります。二次市場や規制の壁で影響は限定的でしたが、2019〜2020年のDeFi勃興でMakerDAOがオフチェーン資産の担保受け入れを開始し、CentrifugeがTinlakeで中小企業の売掛金をオンチェーン化するなど実装が進みました。2021年にはMapleやTrueFiが無担保・信用貸付に挑み、2022年以降は金利上昇を背景に米国債トークン化が加速。2023年は「RWA Year Zero」と称され、ブラックロックやフランクリンなどの伝統金融大手が参入し、検証段階から拡大フェーズへ移行しました。
RWAの概念と資産分類
RWAは現実世界の有形・無形資産をトークンに変換し、移転・保有・活用をデジタル化する取り組みです。狭義のRWAはステーブルコインを除外し、国債・社債などの債券、株式やファンド持分、不動産、私募・私債、サプライチェーン債権、コモディティ、知財や美術品まで幅広く対象にします。とりわけ米国債のような標準化資産は法的枠組みが整備され、トークン化との親和性が高い一方、不動産やアートは権利同期・評価・流動性の難易度が高いのが現状です。
メジャー案件のレビュー
債券系ではOndo(OUSG)、Superstate(USTB)、BackedなどがSPVやファンドを用いた適法構造で展開し、24時間取引や自動決済を実現しています。信用貸付系ではMaple、Goldfinch、TrueFi、Centrifuge、Credix、Clearpoolが、オフチェーン審査とオンチェーン流動性プールを組み合わせ、年8〜18%程度の利回りを提示しつつ、相応の信用リスクを引き受ける設計です。コモディティではPAXGやXAUTが金を1:1裏付けでトークン化し、流動性の高いエクスポージャを提供しています。
市場規模とダイナミクス
2020年に2億ドル未満だった非ステーブルRWAは、2024年中頃に120億ドルを超え、2025年上期には233億ドル規模、8月時点で約252億ドルに拡大しています。最大セグメントは米国債などの公債で約27%を占め、次点に私募信用が続きます。株式・ファンドやコモディティは依然として小粒ですが、基盤整備の進展で拡大余地が残ります。
規制動向の俯瞰
米国はSECの既存証券法枠組みを適用し、Reg D/Reg Sなどの私募・域外発行が中心で、実務は機関投資家向けが主流です。EUはMiCAで資産参照型トークンを制度化し、SICAV等のビークルを活用した適法発行が広がっています。シンガポールはMASのProject Guardianやサンドボックスで試行を後押し、香港はプロ投資家向けのパイロットを解禁。UAEはVARA/ADGMの包括枠組みで発行・保管・取引を整備し、中東のRWA拠点を目指しています。
コストと利回りの比較視点
国債トークンは基礎利回りが金利水準に連動し、管理・カストディ・適法化コストが薄いぶん安定収益の“金利アンカー”として機能します。私募信用はデューディリジェンス・法務運用コストが嵩む一方、8〜15%の厚めの利回りで投資家を惹きつけます。不動産は権利同期や継続管理の費用が重く、収益は賃料配当中心で地域差が大きい構造です。結果として、高利回り資産ほど流動性は乏しく、流動性の高い資産ほど利回りは薄いというトレードオフが表れます。
直面するコア課題
最大の論点は適法性と権利同期、オフチェーン資産の真正性・信用リスク、そして市場流動性の欠如です。価格算定とオラクルの運用も難所で、NAVの遅延やデータ源の不統一が清算リスクを増幅し得ます。これらは技術だけでなく、保証・保険・担保・回収などのオフチェーン手当てを含む総合設計が不可欠です。
BenFenの「ワンクリックRWA発行」
BenFenは2025年8月の大型アップデートで、安定通貨に加えRWAのワンクリック発行を標準化しました。高TPSとサブ秒確定、Move系VM最適化、カストディ・KYC・監査の組み込みフローにより、SPV資料や評価書・保管証憑のハッシュ固定を前提に、適格投資家向けの募集・分配を自動化します。ガスのステーブル支払いとスポンサー機構、クロスチェーン接続により、発行の技術障壁と時間コストを大幅に低減しつつ、他チェーンへの波及も視野に入れています。
まとめ
RWAは「青い海」と「赤い海」の狭間に立つ巨大テーマです。法務・真正性・流動性という岩礁を回避しながら、国債と私募信用を両輪に市場が拡大してきました。今後は、標準化された発行・保管・開示と高信頼オラクル、そして適法な投資家アクセス経路の整備が鍵になります。BenFenのようなインフラがプロセスを標準化し、実務を自動化することで、RWAはコンセプトから基盤産業へと進化し、伝統金融とクリプトを結ぶ本格的な橋梁になっていくと見込まれます。
Avalanche、エンタープライズ向けブロックチェーン採用を牽引
はじめに
2025年、グローバル大企業のブロックチェーン参入が再び加速しています。2021年のNFTバブル期とは異なり、今回は実需と規制の明確化が支えとなっています。ETF承認、EUのMiCA施行、米国FIT21法案などにより不確実性が解消され、ステーブルコイン市場はVisaやMastercardの決済規模を凌駕しました。この背景の下、J.P.モルガンやブラックロックなどは投機的アプローチではなく、RWAトークン化や決済、国際送金といった具体的な領域で成果を出しています。
本稿では、Tiger Researchが提示する「5段階導入フレームワーク」を基に、Avalancheがなぜ企業ブロックチェーン採用の中心的選択肢となっているのかを解説します。
機関参入の第二波
NFTブームではナイキやアディダスなどが参入し短期的成功を収めましたが、FTX崩壊や規制不透明性から多くが撤退しました。その後の「クリプト冬」を経て、2025年の再参入は構造的に異なります。規制整備に支えられ、ステーブルコイン取引高は2024年に27.6兆ドルと、既存決済ネットワークを超過。ブラックロックのBUIDLファンドが半年で29億ドルを集めるなど、確実な成果も出ています。
導入フレームワーク(5段階)
-
ビジネス課題の検証
- 既存手段では解決できない領域かを確認し、RWAや決済、ゲーム、ロイヤルティ領域でユースケースを明確化します。
-
組織能力の評価
- 専任チームや既存ITとの親和性を点検。スマートコントラクトや不変性といった特性理解が必須です。
-
ブロックチェーン選定
- ファイナリティ、サポートリソース、導入事例、セキュリティ、コストの5基準で評価。誤った選択は高額な移行コストを生みます。
-
段階的実装
- MVPから開始し、検証と改善を重ねながら機能を拡張することが成功の鍵です。
-
エコシステム統合と拡大
- 既存システムや外部パートナーとの連携を進め、産業横断的な透明性と新たな価値創造へつなげます。
Avalancheの構造的優位性
Avalancheは「ネットワークのネットワーク」と呼ばれる独自アーキテクチャを持ち、従来チェーンのスケーラビリティ問題を解消します。
- P-Chain:新規チェーンの作成・管理を担う「都市計画局」
- C-Chain:EVM互換のスマートコントラクト実行環境、Ethereum資産の移植が容易
- X-Chain:条件付き資産や複雑な金融商品の実験場
- ICM:チェーン間相互接続を可能にし、ネットワーク効果を最大化
この並列構造により、混雑耐性と柔軟なユースケース対応を両立しています。
Avalancheを選ぶ理由
- ファイナリティ:約2秒で確定。決済通知が即時可能。
- リソース:Ava Labsは280名超の組織規模を持ち、地域別サポートを展開。
- 導入事例:シンガポールMAS承認のStraitsX決済、米ワイオミング州の公的ステーブルコイン、ネクソンのメイプルストーリーユニバースなど。
- セキュリティ:独立L1運用で障害分離、権限付きバリデータによる51%攻撃排除、eERCによる秘匿性。
- コスト構造:手数料は数セント水準、AvaCloudによりノーコードで専用チェーン構築可能。
実用事例
- RWA:KKRのヘルスケアファンドをSecuritize経由でトークン化。複雑な規制要件を満たしつつ透明性を実現。
- 決済:StraitsX×Alipay+×GrabPayがAvalanche上でリアルタイム決済を実現。観光客が自国アプリで支払い、加盟店は即時XSGDで決済可能。
- ゲーム:ネクソンのMapleStory UniverseがAvalanche上に構築。1日85万件超のトランザクションを処理し、プレイヤー資産権を実現。
- 消費者向け:サントリー「ボウモア」NFT認証システム。NFCタグとNFTを組み合わせ、真贋証明・所有権確認・消費データ収集を同時に実現。
AvaCloudの役割
2023年開始のAvaCloudは「ブロックチェーン版AWS」とも呼ばれ、数クリックで専用L1を構築可能にしました。FIFAやSK Planet、サントリーなども採用し、技術よりビジネス課題解決に注力できる環境を提供しています。
まとめ
Avalancheは高速ファイナリティ、堅牢なサポート体制、豊富な実績、セキュリティ分離、低コスト運用という5条件を満たし、RWA、決済、ゲーム、消費者分野で実用成果を出しています。とりわけAvaCloudの普及により、「どう作るか」ではなく「何を作るか」というフェーズへと移行しました。
企業にとってAvalancheは、単なる技術選択ではなく、信頼できる基盤パートナーとして、ブロックチェーン産業化の扉を開く存在となっています。
Kaito、予測市場から「情報市場」への進化を牽引
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >



