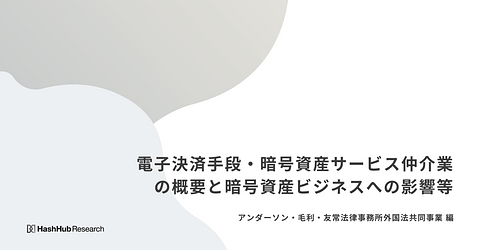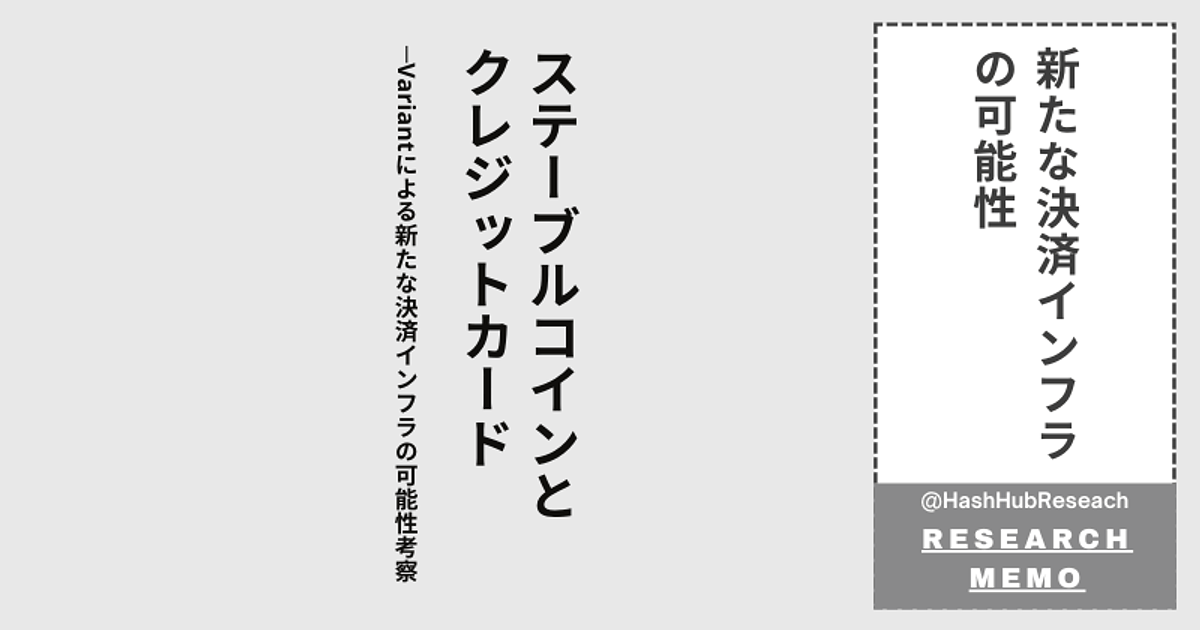
ステーブルコインとクレジットカード|Variantによる新たな決済インフラの可能性考察を読む
2025年08月15日
リサーチメモ(Lawrence)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- ステーブルコインが主流になるための二段階ステップ
- ステップ1:ニッチなユーザー層の痛点解決から始める
- ステップ2:分断された利用をオープンなネットワークで集約する
- トークンとエクイティの役割分担――オンチェーンとオフチェーンの価値
- この記事から得られる示唆
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
金融とテクノロジーの融合が進む現代、私たちの「お金の使い方」は大きな転換期を迎えています。ステーブルコインは、クレジットカードに取って代わる決済手段となり得るのか――この問いに対し、Variantの最新記事は具体的なシナリオと鋭い洞察を提示しています。今回は、この記事で語られている内容を解説します。
参考:Stablecoins v. Credit Cards
本稿を読むことで、読者は「新しい決済インフラの普及には、技術革新だけでなくユーザーの課題解決やネットワーク効果、規制対応など多面的な視点が不可欠である」ことを改めて認識できるはずです。
近年、暗号資産の中でもステーブルコインは決済手段として注目を集めています。特に米国ではクレジットカードが圧倒的なシェアを持つ中で、「ステーブルコインがカードを置き換えることは可能なのか?」という問いに対し、本記事では独自のシナリオと示唆が語られています。
ステーブルコインが主流になるための二段階ステップ
記事では、「多くの人はステーブルコインの役割を、クレジットカードのバックエンド決済効率化に限定して考えているが、実際にはカードそのものを置き換える可能性がある」と主張しています。そのための道筋として、Visaが普及した過程を参考に二段階のステップを提示しています。
ステップ1:ニッチなユーザー層の痛点解決から始める
具体例として、米ドルへのアクセスが制限されているラテンアメリカ諸国などでは、ステーブルコインが「ユニークな利便性」を提供し、米国のECサイトでの購入を容易にします。
また、リワード重視のユーザー層に対しては、ホワイトラベル型ステーブルコインを用いた報酬プログラムが有効であり、「消費者は強力なリワードがあれば、多少のオンボーディングの手間を許容する」と指摘しています。これは、スターバックスのリワードや、アーティストのファン向けの特典など、既存の事例にも通じます。
また、リワード重視のユーザー層に対しては、ホワイトラベル型ステーブルコインを用いた報酬プログラムが有効であり、「消費者は強力なリワードがあれば、多少のオンボーディングの手間を許容する」と指摘しています。これは、スターバックスのリワードや、アーティストのファン向けの特典など、既存の事例にも通じます。
ステップ2:分断された利用をオープンなネットワークで集約する
こうしたニッチな普及が進むと、チェーンや発行体、消費者保護の基準などが分断された状態(fiefdoms)が生まれると予想しています。この分断を解消するためには、「中立的で相互運用可能なネットワーク、いわばステーブルコイン版Visaのような存在が必要」と述べています。
個別のエッジケースの成功体験をつなぎ合わせることで、十分な供給と需要を集約し、「新しい決済手段のブートストラップ問題」を解決できるという示唆です。
個別のエッジケースの成功体験をつなぎ合わせることで、十分な供給と需要を集約し、「新しい決済手段のブートストラップ問題」を解決できるという示唆です。
この流れは、クレジットカードが普及した初期の歴史とも重なります。カードは最初から全ての消費者に受け入れられたわけではなく、特定の利点(利便性や報酬)を武器に一部の層から広がり、その後ネットワーク効果によって主流になりました。ステーブルコインも同様に、まずは「周辺的なニーズ」を満たし、それらをつなげることで、最終的には「カードの代替」としての地位を築く可能性があると論じています。
トークンとエクイティの役割分担――オンチェーンとオフチェーンの価値
記事ではさらに、暗号資産業界における「トークンとエクイティ(株式)の役割分担」についても言及しています。筆者は、
- オンチェーンの価値はトークンへ
- オフチェーンの価値はエクイティへ帰属させるべき
とし、その理由として「トークンはデジタル資産の自己所有権を可能にし、ユーザーが直接資産やプロトコルをコントロールできる」ことを挙げています。一方、オフチェーンの収益や資産は、トークン保有者が直接所有・コントロールできないため、株主に帰属させるのが適切だと述べています。
この区別は、SEC(米証券取引委員会)の規制によって歪められてきた歴史があるものの、「今後はトークンの可能性を最大化する方向へと変化が求められる」と記事は強調しています。