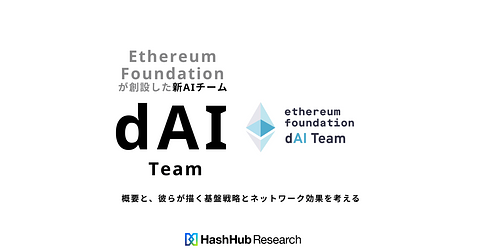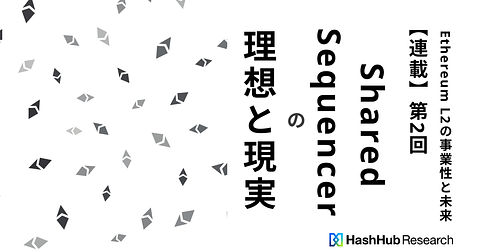イーサリアムの新トランザクションメカニズム『シールドトランザクション』とは|Anders Elowsson氏の提案を解説
2025年03月11日
リサーチメモ(masao i)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
Ethereum(以下、イーサリアム)のコミュニティで提案されたMEVからトランザクションを保護するトラストレスな仕組みとして提案(2025年3月)された「Sealed Transactions(シールドトランザクション)」という新しい提案について、まだ馴染みのない方にも伝わるような解説が必要だと感じ、小難しい数式は抜きにその開発動機とメカニズム、何を目的にした提案なのかを提案者資料をもとにざっくりとまとめました。筆者自身、特定の立場やサービスを推奨する意図はなく、あくまでも一視点として情報を整理・紹介することで、読者の皆様がより公平な視点からこの仕組みを知り、考えるきっかけになればと思っています。