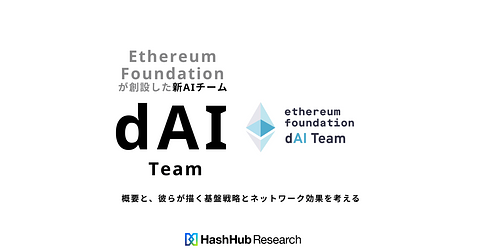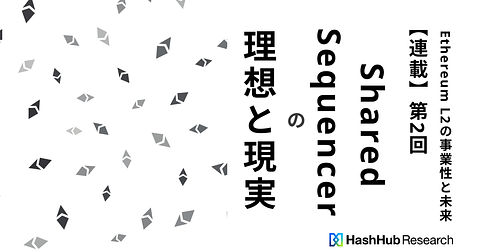EthereumにおけるMEV問題と「分散型ランダムブロック提案」の解決策
2025年03月11日
リサーチメモ(masao i)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
Ethereum(イーサリアム)はブロックチェーン上の取引処理において、MEV(最大抽出可能価値)と呼ばれる問題を抱えています。MEVとは、ブロック提案者(かつてはマイナー、現在はPoSバリデータ)がトランザクション(取引)の順序や選別を操作することで追加で得られる利益のことで、DeFi取引などが増える中で無視できない存在となっています。
※関連有料レポート:図でわかるMEV入門
このMEVを狙って高度なボットやブロック提案者が暗躍し、通常のユーザーに不利益を与えるケースが後を絶ちません。本記事では、EthereumのMEV問題の具体例と、これを解決するために提案された新しいメカニズム「Decentralized Random Block Proposal(分散型ランダムブロック提案)」の仕組み・目的を整理し、特にMEV対策とEthereumの民主化への影響について分かりやすく解説します。
- 提案資料(提出日:2025年2月28日):Decentralized Random Block Proposal: Eliminating MEV and Fully Democratizing Ethereum
- 提案者:malik672