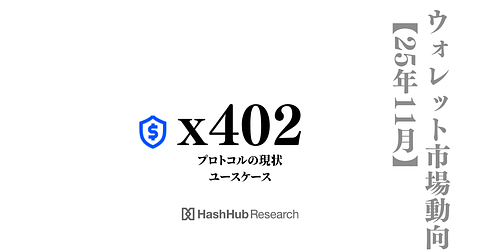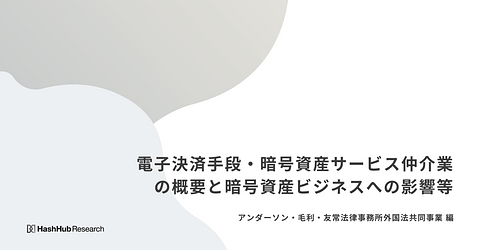Base上のプライバシーアプリ「Fluidkey」の概要とそのビジネスモデル
2025年03月06日
リサーチメモ(masao i)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- はじめに
- Fluidkey技術の仕組み
- 他のプライバシー技術との違い(Monero、Zcash、Umbra)
- Fluidkeyが提供するユニークな機能
- Fluidkeyのビジネスモデル
- Fluidkeyはどこで収益を上げるのか?
- 競争優位性と市場での立ち位置
- 今後の展望
- 規制リスクと市場の反応
- 今後の成長の可能性と普及のカギ
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
Fluidkeyは、暗号資産の取引や送金におけるプライバシー保護に特化した、新しいウォレットアプリです。複数の国のAML(マネーロンダリング対策)規制に対応しつつ、取引ごとに使い捨ての新しいアドレス(ステルスアドレス)を自動生成し、受け取った資金をユーザー自身のみが管理できる仕組みを採用しています。これにより、外部の第三者から見ると、毎回異なるアドレスへの送金に見えるため、誰が最終的な受取人か分からなくなるわけです。まるで「匿名の郵便受け」を毎回作ってお金を受け取るようなイメージです。
このBase上で動作するこのサービスの仕組みやビジネスモデルが気になり、AIを活用してその概要と類似プロジェクトとの比較調査してもらいました。(余計な喩えありの)カジュアルな文体ですが、参考までにどうぞ。
Fluidkey
このBase上で動作するこのサービスの仕組みやビジネスモデルが気になり、AIを活用してその概要と類似プロジェクトとの比較調査してもらいました。(余計な喩えありの)カジュアルな文体ですが、参考までにどうぞ。
- Fluidkey website:https://www.fluidkey.com/
- X:https://x.com/fluidkey
- Docs:https://docs.fluidkey.com/
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >