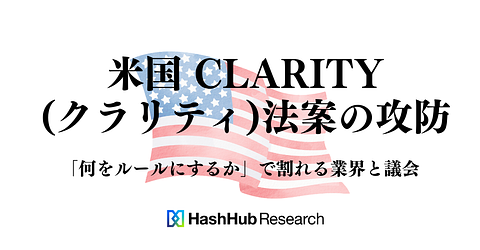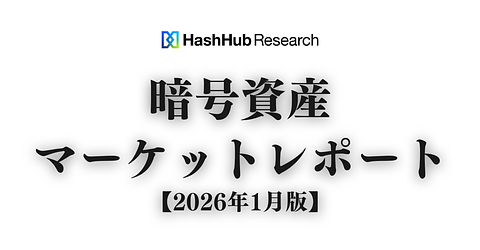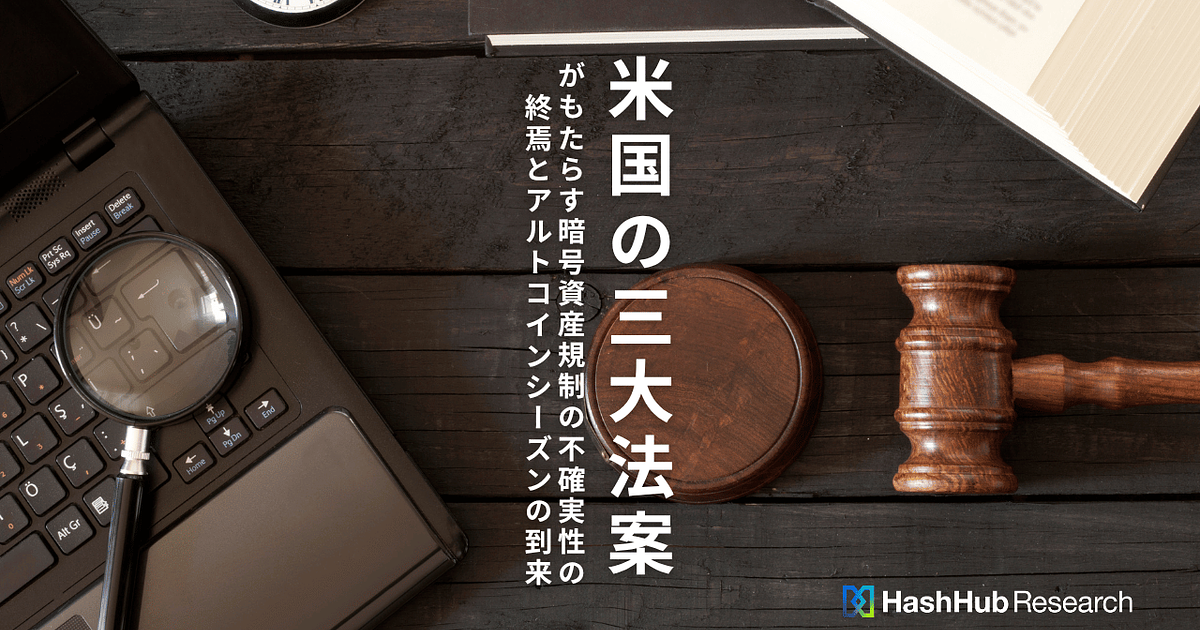
米国の3大法案がもたらす暗号資産規制の不確実性の終焉とアルトコインシーズンの到来
2025年07月18日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 法案概要
- 1. GENIUS法(S.1582):ステーブルコインの信頼性担保と制度化
- 2. 市場構造明確化法案(CLARITY Act, H.R.3633):管轄権の境界線を描く
- 3. Anti-CBDC法(H.R.1919):政府の役割に一線を画す
- 包括的インパクト分析:3法案が織りなす市場へのインパクト
- 立法プロセスと成立の可能性
- 投資家への示唆まとめ
- 総括
2025年、米国の暗号資産市場は、歴史的な規制の枠組みが形成される重要な岐路に立たされています。
現在、米国議会では、
- ステーブルコインを包括的に規制する「GENIUS法」
- デジタル資産の「商品」と「証券」の区分を明確化する「市場構造明確化法案(CLARITY 法)」
- 連邦準備制度(FRB)による中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行を禁じる「Anti-CBDC法」
という、性質の異なる3つの法案の審議が一体的に進められています。
筆者作成
これらは単なる個別の規制案ではありません。三者が組み合わさることで、「政府発行のデジタルドルは作らず、厳格な監督下で民間発行のデジタルドル(ステーブルコイン)を育成する」という、米国の国家的なデジタル通貨戦略の狙いが垣間見えます。
これらは単なる個別の規制案ではありません。三者が組み合わさることで、「政府発行のデジタルドルは作らず、厳格な監督下で民間発行のデジタルドル(ステーブルコイン)を育成する」という、米国の国家的なデジタル通貨戦略の狙いが垣間見えます。
本レポートでは、これら3法案の概要を詳細に解説し、立法プロセスの現状と政治的背景を解説します。
投資家向けの結論からいえば、筆者はETHをはじめとするアルトコイン・バブルのような市場環境のきっかけになり得る動向だと考えています。ただし、「何でも上がるバブル相場」とはならず、顕著な動きを見せるのは、法案の内容に照らし合わせたある種の適格性のあるアルトコインに限定されるものと思われます。
なお、なぜこれだけ米国は暗号資産の規制明確化に積極的なのか?という疑問については以下のレポートにて考察しています。
関連レポート;ステーブルコインは“国債吸収装置”となるか?利回り・規制・マクロ需給の実証とアーサー・ヘイズ氏の視点
なお、なぜこれだけ米国は暗号資産の規制明確化に積極的なのか?という疑問については以下のレポートにて考察しています。
関連レポート;ステーブルコインは“国債吸収装置”となるか?利回り・規制・マクロ需給の実証とアーサー・ヘイズ氏の視点
法案概要
1. GENIUS法(S.1582):ステーブルコインの信頼性担保と制度化
※準備金構成は例
Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Actの一部を切り出したこの法案は、決済用ステーブルコインの発行者に銀行に準ずる、しかしより柔軟な規制を課すことを目的としています。
-
主要条項:
- 100%準備金要件: 発行される全てのステーブルコインに対し、1対1の比率で「質の高い流動資産(High-Quality Liquid Assets)」による裏付けを義務付けます。これには現金、連邦準備銀行への預金、短期米国債、そして財務省が定める適格なレポ取引などが含まれます。これにより、Tether社などが抱える準備金の透明性問題に終止符を打ち、取り付け騒ぎのリスクを最小化します。なお、すべての適格レポ取引が必ず含まれる訳ではなく規制次第となります。
- 二元的な監督体制: 発行者は、その規模に応じて州または連邦の監督当局から免許を取得する必要があります。発行額が100億ドル以下の事業者は州当局の監督を選択できますが、100億ドルを超える大手発行者は原則として連邦監督(通貨監督庁など)の対象となります。
- 詳細な情報開示と監査: 準備金の構成、償還方針、リスク管理体制に関する詳細な情報を定期的に公衆に開示し、独立した監査法人による証明を受けることが義務付けられます。
- 証券・商品からの除外: この法律の要件を満たす決済用ステーブルコインは、証券法上の「証券」や商品取引法上の「商品」の定義から明確に除外されます。
GENIUS法は、Circle社が発行するUSDCのような、規制準拠を志向するステーブルコインにとっては強力な追い風となります。
法的なお墨付きを得ることで、機関投資家や大手金融機関が安心して利用できる決済手段としての地位を確立します。
一方で、準備金の構成が不透明であったり、規制の緩いオフショアを拠点としたりする事業者には、米国市場からの実質的な締め出しという形で淘汰圧力がかかるでしょう。
2. 市場構造明確化法案(CLARITY Act, H.R.3633):管轄権の境界線を描く
※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。