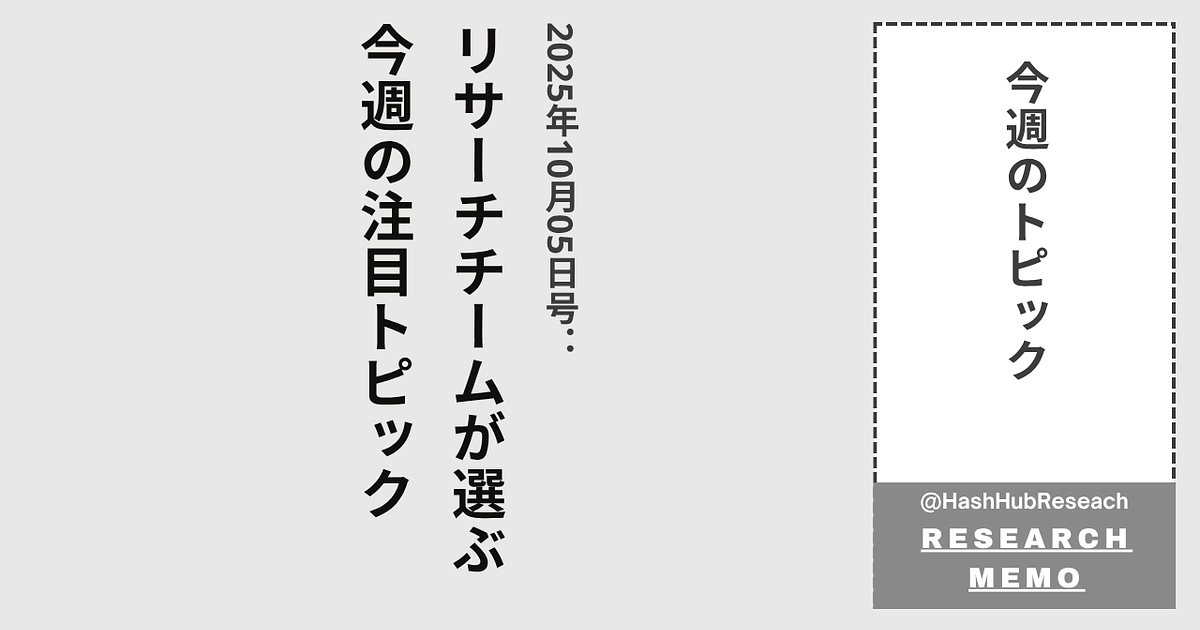
リサーチチームが選ぶ今週の注目トピック 2025年10月5日号
2025年10月05日
リサーチメモ(derio)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 前提
- 今週1週間分のニュースを紹介
- ▍Pantera Capital、SolanaのDATを設立しSOLを戦略的に取得
- ▍Ethereum、L1からの移行を加速させる「Rollup-Centric」戦略
- ▍2025年版CoinGeckoビットコインレポート
- ▍ロボット産業とブロックチェーン技術の融合が加速している現状を分析
- ▍クリプトのアイデンティティ危機、金融商品か新たな環境か
- ▍「注目」を経済的価値に変える新指標「Attention」
- ▍ロールアップの収益モデルとその持続可能性
- ▍Pump.fun、ストリーミング分野でTwitchに対抗する新時代へ
- ▍Plasma war room-$XPL TGEの取引に関するメモ
- ▍「低リスクDeFi」はオンチェーン金融の基盤を築く|ETHのリステーキングを組み合わせれば、“世界の基準金利”をオンチェーンに移す革命につながる
- ▍ネットワーク国家か、国家のネットワークか
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
前提
本レポートでは、最新のクリプトやWeb3市場、オピニオンに関する記事やスレッドをまとめています。各記事の要点を把握し、トレンドやインサイトを効率的にキャッチアップできる内容となっていますので、ぜひご活用ください。
また、本シリーズは今週1週間分のニュースをまとめたものになります。リアルタイムで情報をキャッチアップしたい方は、「HashHub Research ニュース」をご利用ください。
今週1週間分のニュースを紹介
▍Pantera Capital、SolanaのDATを設立しSOLを戦略的に取得
要旨
Pantera Capitalが主導し、Nasdaq上場のデジタル資産トレジャリー「Solana Company(ティッカー:HSDT)」を立ち上げました。非公開増資で5億ドル超を調達し、最大12.5億ドル超の資金調達余地を確保しています。目的は「1株あたりのSOL保有量(SOL per share)を最大化」し、商用性の高いSolanaエコシステムへの上場市場経由のアクセスを提供することです。
DAT(Digital Asset Treasury)という投資ビークル
DATは、現物やETFの単純保有と異なり、資本市場取引と運用収益でNAVを増やし「基礎トークン保有量を時間とともに増やす」設計です。BitMineなどの先行事例では、トークン当たり保有量の大幅増加を実現しており、DATが単なるエクスポージャーではなく“プロダクティブな保有”になり得る点が強みです。
HSDTの成長ドライバー(SOL per share最大化)
HSDTは二つの経路でSOL per shareを強化します。第一に資本市場アクション(プレミアム発行、ボラティリティを用いたCB活用、NAV割れでの自社株買い)。第二に収益化(保有SOLのステーキングとDeFi利回り獲得)。Solanaのネイティブ利回りは概ね年率7%で、個人には煩雑な運用を上場車両が一括で代行します。結果として、mNAV拡大→株価の上昇余地、に加えてSOL自体の価格上昇もリターンに寄与します。
Solanaを選好する理由
Solanaは高スループット(数千TPS)、~400ms級の最終性、手数料<$0.01により、消費者向けアプリやDeFiの土台として拡張余地が大きいです。開発者流入とアクティブウォレットの増加、手数料バーンによる供給面の改善、主要金融機関のRWA・決済実装の採用実績が、基盤としての信頼性を高めています。
機関投資家のアロケーション・ギャップ
機関保有比率や企業トレジャリー組入れは、BTC・ETHに比してSOLが著しく低く、未配分余地が大きいです。性能・採用指標に対して資本配分が追いついていない“キャッチアップ・トレード”が想定され、HSDTのような公開車両が受け皿になり得ます。
直近の進展
9月中に5億ドル超の資金調達、約76万SOLの購入実行、社名をSolana Companyへ変更しSolana FoundationとのLOI(意向表明)を発表しています。資本投入→現物取得→ブランド明確化の順で、上場車両としての体制を整備しています。
位置づけとリスク
HSDTは「SOLエクスポージャー+アクティブなNAV成長」を提供するDATです。一方で、トークン価格ボラティリティ、ステーキング/DeFiの運用・カストディ・流動性リスク、株価と基礎資産の乖離(プレミアム/ディスカウント変動)、規制・会計基準の変化などが主なリスクです。管理チームの執行力が差別化要因であり、資本市場手段と運用の配分最適化が鍵になります。
関連トピックのハイライト
Ripple×SecuritizeがBUIDL・VBILLの持分をRLUSDへスワップ可能にするスマコン構想を発表しました。PayPalはP2P支払いリンクに暗号資産連携(BTC/ETH/PYUSD)を予告しました。SECは暗号ETFの汎用的上場基準を承認し、新規ETFのローンチ加速が見込まれます。Raikuは1,350万ドルを調達、Krakenは「Kraken Launch」でICO参加機能を案内、カザフスタンはテンゲ連動の新ステーブルコイン「Evo」を計画中です。PanteraはSolanaの投資魅力に関するインタビュー露出を強化しています。
まとめ
HSDT(Solana Company)は、上場という透明な器で「SOL per shareの逓増」を目指すDATです。Solanaの性能・採用トレンド、機関アロケーションの未充足、資本市場アクションと運用収益の二重エンジンが、単なる現物保有やETFでは得にくい超過収益の余地をもたらします。カテゴリ(DAT)自体は黎明期ですが、運用・資本市場・ガバナンスの設計を磨けば、Solana版“準ソブリン級トレジャリー”としての地位確立が期待できます。
▍Ethereum、L1からの移行を加速させる「Rollup-Centric」戦略
要旨
本稿は「空港(L1)と航空会社(L2)」の比喩で、独自L1を維持するコスト・流動性・検証者運用の重さと、Ethereumに寄り添うL2(ロールアップ)の機動性・到達可能性を対比し、なぜ既存L1がEthereumへ回帰・移行しつつあるのかを技術・経済の両面から整理しています。結論として、独自の信頼モデルや非EVM実行、特殊なガバナンスが要らない限り、L2で「飛ぶ」方が合理的だと述べます。
ロールアップ中心設計を後押しするアップグレード
- EIP-4844(Dencun)でロールアップデータをblobに分離し、約95%のデータコスト削減を実現しました。
- EIP-7691(Pectra)で1ブロック当たりのblob目標を拡張し、混雑時の手数料上振れを緩和しました。
- EIP-7594(PeerDAS)でデータ可用性サンプリングを導入し、ホームステーカーの要件を増やさずにblob供給を段階的に増やせる見込みです。
- EIP-7732(ePBS)で提案者–ビルダー分離をプロトコル内に取り込み、検閲耐性と中立性を高めます。
- Verkle Trees / EOFで検証コストと証明データを縮小し、L1ノード参加のハードルを下げます。
これらの積み上げにより、L2の粗利は80–95%へ、1トランザクション当たりのユーザー手数料は数十セントから数円台まで低下し、ロールアップはソフトウェア的な損益構造に近づいています。
経済性:L2は“フィンテック型”のユニットエコノミクス
ロールアップの収益はユーザーのL2ガスや優先実行スロット販売、MEVの一部捕捉などです。コストは主にblob料金・L1ガス・証明コストで、Dencun以降は日次数千〜数十万ドル規模に縮小しました。結果、BaseやArbitrumは日次収益を維持しつつ、R&Dやグラントを営業キャッシュフローで賄いやすくなっています。
独自L1の重荷:検証者・セキュリティ・流動性
大規模PoSの年次セキュリティ予算は数十億ドル規模です。新興L1は検証者獲得のためにインフレと報酬を積み増し、さらに流動性・上場・ブリッジを一から構築する必要があります。対してL2はEthereumの検証者多様性と流動性を即時に継承できます。
事例:移行が示す合理性
- Ronin:少数検証者によるブリッジ侵害を経て、zkEVM L2化でL1級セキュリティとサブ秒体験を両立しました。
- Celo:OP Stack L2化で年2000万ドル規模の検証者コストを削減し、EigenDA活用でさらにコスト最適化、L1のDeFi流動性へ直結しました。
- Lisk:EVM標準への集約に合わせてOP Stack L2へ転換し、ツール・ウォレット・カストディ・DeFiと即時互換を獲得しました。
一方で、dYdXのように実行環境そのもの(例:高性能CLOB)が製品である場合は主権チェーンが適合します。
流動性分断と“インテント”による解消
ロールアップ間では流動性が分散し、楽観的ロールアップの7日退出がUXの摩擦になります。これに対し、Across / Everclear / UniswapXなどがインテント駆動で資本効率よく充当し、会計のみを相殺して実質即時を実現しつつ、最終は正統ブリッジで清算します。
標準化も進み、ERC-7683(クロスチェーン・インテント)、ERC-3770(チェーン識別付きアドレス)、CCIP-Readが一体的UXを後押しします。
L2はEthereumを“食わず、太らせる”
全ロールアップは最終的にL1へアンカーし、blob手数料・証明検証・プロポーザーTipsでETH需要とバーンを押し上げます。based rollup設計ではL2由来MEVがL1へ自然流入し、LineaのETHバーンのように明示的な価値還流も登場しています。L2拡大はL1のネットワーク国家的モデル(憲法=コンセンサス、最高裁=検証、通貨=ETH)を強化します。
いつL1を続けるべきか
独自の信頼境界(規制・許可型)、非EVM実行、L1レベルのガバナンス実験など、L2では歪みが大きい要件がある場合は主権維持が妥当です。そうでなければ、製品速度・到達可能性・資本効率でL2が優位です。
まとめ:空港はできた、あとは飛ぶだけです
Ethereumは中立で薄いコアを磨き、実行はエッジ(L2)へという分業を徹底しています。結果、コスト低下→需要増→L1手数料増とETHバーンの好循環が進み、既存L1の“Ethereumアライン”が加速しています。ユーザーは安い・速い・安全を望み、開発者は流動性・ツール・利用者を望みます。その期待値に最短で応える道が、Ethereum上で飛ぶ(L2化する)ことです。
▍2025年版CoinGeckoビットコインレポート
要旨
本レポートは、ビットコインの価格サイクル、ネットワーク活動、ETF・取引所・各国での採用、そしてマイニングや企業財務での位置づけまでを俯瞰し、資産・ネットワークの両面で成熟が進んでいることを示しています。半減期ごとの新高値更新という長期トレンドは続きつつも、上昇倍率は逓減しており、代わりにETF・企業財務・ハッシュレートといった“基盤需要”が主役になりつつあると読み解けます。
半減期サイクルと価格ダイナミクス
2009年以降、半減期のたびに供給増加ペースが低下し、報酬は25BTCから3.125BTCへと87.5%減少しました。価格は2025年9月1日時点で約10,9万ドルに達し、各サイクルで新高値を更新してきましたが、上昇幅は2017年29倍 → 2021年6.7倍 → 2025年+93.1%(年初来ベース)と縮小傾向です。なお、2024年3月には半減期前に7.34万ドルのATHを記録しており、サイクル構造の前倒しも観測されています。
他資産との比較と相関の変化
2024年はBTCが+119%と株式指数(S&P500+24.0%、ナスダック+30.8%)を大きくアウトパフォームしました。2025年はBTC+16.3%と伸びが落ち着く一方、株式との相関は0.75 → 0.86へ上昇しています。金は2025年に+31.7%と強含みで、BTCとの相関は0.64 → 0.53へ低下し、ディカップリングが進みました。米ドルは2025年に−10.4%と軟調です。
ネットワーク活動と新ユースケース
アクティブアドレスはベア相場を経て回復し、2025年8月に94.4万件へ。2023年以降はOrdinals や BRC-20の波及でユーザー数が価格以外のエコシステム要因にも連動しやすくなりました。ネットワーク活動が価格に先行する局面はなお存在しますが、“手数料・ブロック容量を消費する新用途”が需給に影響する比重も高まっています。
米国スポットETFの資金フロー
2024年の承認以降、10/11本のETFで累計+544億ドルの純流入、保有は129万BTC(供給の約6%)に達しました。グレースケール転換ETFのみ約95億ドルの純流出です。ブラックロックのIBITはAUMシェア52.6%、出来高シェアも22.1% → 75.4%へ拡大しており、現物需要の機関化が顕著です。
マイニング:1ゼタハッシュ突破と地政学
ハッシュレートは2025年4月に1ゼタハッシュを突破、8月4日に1.085ZHのATHを記録しました。2024年初からの伸びは+53.2%(555M TH/s → 851M TH/s)です。米国では政策環境を背景に設備投資が進み、中国系メーカーの米国移転や既存事業者の再エネ志向が加速しています。Eric Trump共同設立のAmerican Bitcoin CorpのNasdaq上場も象徴的です。
企業財務での採用:100万BTCの節目
上場企業による保有は102社で100万1,953BTC(供給の約5%)に到達し、Strategy(旧MicroStrategy)が63万2,457BTCで先頭を走ります。Twenty Oneは5月以降で4万3,514BTCを積み上げ、KindlyMDは合併で5,764BTCを取り込みつつ50億ドルの調達計画を発表。日本のMetaPlanetや欧州のTreasury BVも大口化し、企業トレジャリーとしてのBTCが世界的に定着しつつあります。
投資家への示唆
ビットコインはサイクルごとの上昇倍率が逓減する一方で、“現物ETF・企業財務・ハッシュレート”というストック型の需要柱が太くなっています。短期は株式との高相関がボラティリティを左右する可能性が高いですが、中期ではETF買い・コーポレート需要・マイニング投資が需給を下支えしやすい構図です。ネットワーク面ではOrdinals等の新用途が手数料・活性度に影響し、マクロ面では金との相関低下が分散効果を再評価させます。
リスクと留意点
価格は依然としてマクロ政策・規制動向・米株との相関の影響を強く受けます。ETFフローの反転、マイニングコスト上振れ、オンチェーン手数料上昇や新用途失速は短期的な逆風になり得ます。とはいえ、供給減(半減期)と制度マネーの受け皿(ETF・企業財務)という二本柱は、長期の需給均衡を改善し続ける可能性が高いです。
▍ロボット産業とブロックチェーン技術の融合が加速している現状を分析
このレポートは有料会員限定です。
HashHubリサーチの紹介 >
法人向けプラン >
【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、
本レポートを無料でご覧いただけます。
本レポートを無料でご覧いただけます。
口座をお持ちでない方はこちら >



