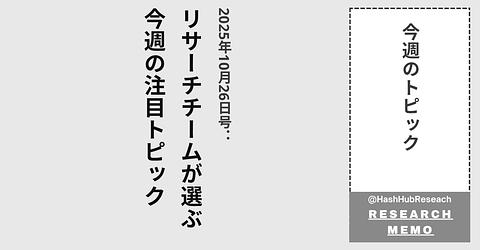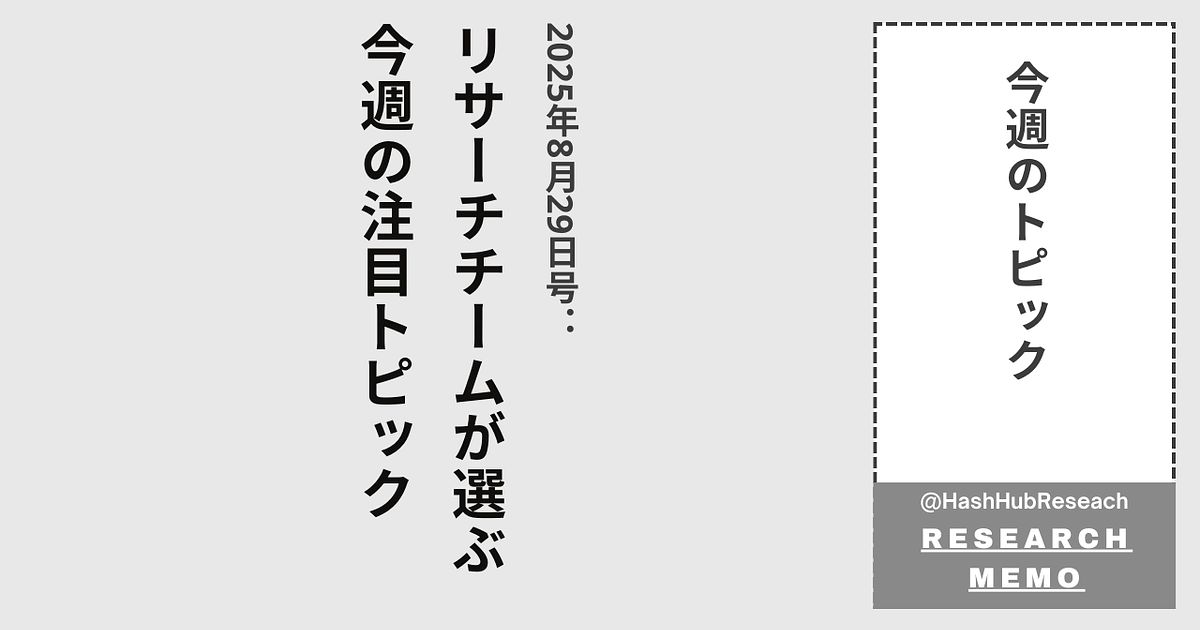
リサーチチームが選ぶ今週の注目トピック 2025年8月29日号
2025年08月29日
リサーチメモ(derio)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
目次
- 前提
- 今週1週間分のニュースを紹介
- ▍DATs(Digital Asset Trusts/デジタル資産トラスト) の収益構造について
- ▍予測市場(Prediction Markets)の現状マッピング
- ▍Soneiumが、新しく「Soneium Score」というユーザー活動を評価・報酬する仕組みを導入
- ▍「バッファロー・ビル」ベッセントのステーブルコイン戦略 by Arthur Hayes
- ▍DragonflyのHaseeb氏によるWebX東京参加後の所感
- ▍Ethereum「EVMからRISC-Vへ」移行構想の要点
- ▍伝統企業がRWAに参入する際のコストと課題
- ▍dYdX Roadmap アップデート
- ▍米国債トークン化市場の現状と課題
- ▍オンチェーンB2B決済を変革する3つの力
- ▍ステーブルコイン市場の多様化と動向
- ▍ステーブルコインの発行者が独自のブロックチェーンを立ち上げる理由
- ▍TONでの公正なロイヤリティ:NFT 2.0
- ▍LEASH v2 – 移行および開発アップデート(保有者同等性 + ターゲットスナップショット)
- ▍Agglayer CDK Enterpriseの概要
- ▍「アテンション」が価値となる新しい経済モデル
- ▍数字やデータのみを重視する「クリプト・ポジティヴィズム」という思想の危険性
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
前提
本レポートでは、最新のクリプトやWeb3市場、オピニオンに関する記事やスレッドをまとめています。各記事の要点を把握し、トレンドやインサイトを効率的にキャッチアップできる内容となっていますので、ぜひご活用ください。
今週1週間分のニュースを紹介
▍DATs(Digital Asset Trusts/デジタル資産トラスト) の収益構造について
DATsの収益構造とその特徴
DATs(Digital Asset Trusts/デジタル資産トラスト)は、しばしば「保険会社」に例えられます。その理由は、収益の源泉が大きく2つに分かれており、保険会社のモデルと似た構造を持っているからです。Mike Ippolito氏はこの点を強調し、DATsの仕組みをより理解しやすく説明しています。
金融工学による収益
まずひとつ目は金融工学による収益です。これは保険会社における「リスクを引き受けることによる利益」と類似しています。具体的には、ボラティリティを売却することでプレミアムを得たり、バランスシート設計によって価値を生み出す仕組みです。DATの場合、BTCを転換社債や優先株、普通株といった形に「ラッピング」し、市場の需給を利用して本来のBTC価格以上で販売することで収益を確保します。
営業収益
二つ目は営業収益であり、これは保険会社におけるアンダーライティング収益に相当します。DATの場合、ステーキング報酬やDeFiにおける利回りなど、資産そのものが生み出す収益がこれにあたります。つまり、資産自体が持つ生産性に依存したリターンです。
現状の課題と構造的リスク
DATの現状にはいくつかの問題点があります。まず、投資家が「利回りの源泉」を十分に見分けられていないことが指摘されます。多くのDATは金融工学に依存しており、アービトラージや新規発行によって既存負債を返す構造を持っています。しかしBTCのボラティリティは構造的に低下しており、マイクロストラテジーのようなモデルでは新しい収益源を生み出しにくい状況です。こうした事情が「ポンジ的ではないか」という批判を生む要因となっています。
今後の展望:2~3年スパンでの変化
今後、投資家はDATの利回りの質に敏感になると予想されます。金融工学に由来する利回りは持続性に乏しく、寿命があります。一方で、資産自体が生む「本源的収益」に基づいた利回りは長期的に評価されやすいです。したがって、営業収益に近い安定した収益を提供できるDATが今後優位に立つと考えられます。
ETH・SOLの優位性と資金調達への影響
ここで注目すべきはETHやSOLのような「生産的資産」です。これらはネットワーク実行レイヤーにおけるトランザクション手数料やMEVリワード、さらにはAaveやMorphoといったDeFiプロトコルでの利回りといった、実需に基づく収益源を持っています。このため、DATがこれらの資産を組み込むことで資金調達を有利に進められる可能性が高いです。
まとめ(TL;DR)
DATは「資産と負債のバランスをとる金融商品」であり、必ず利回りが求められます。その利回りは大きく二つに分けられます。ひとつはボラティリティ売却や新規発行といった金融工学によるものです。もうひとつはステーキングやDeFi利回りといった資産が生む営業収益です。今後は本源的な収益を確保できるDATが評価され、ETHやSOLを基盤とするモデルがBTCよりも構造的に優位に立つと見られています。
▍予測市場(Prediction Markets)の現状マッピング
予測市場の現状と初期的特徴
予測市場(Prediction Markets)は、現在まだ2019年頃のDeFiを思わせるような初期段階にあります。基盤整備や実験の余地が大きく、各プレイヤーが試行錯誤しながら市場を形作っている段階です。ここではその主要な分類と、見えてきた構造的な特徴を整理します。
主な分類
まず大枠として、予測市場のエコシステムは6つのカテゴリに整理できます。中心にあるのはPolymarketやKalshiといったプラットフォームで、これらが全体の流通と利用の軸を担っています。その周囲には、スポーツやニュースなど特定テーマに特化したニッチ市場のアプリ群が登場しています。さらに、流動性を橋渡しする取引フロントやアグリゲーター、ボットといった中間レイヤーも発展しつつあります。
一方で、DeFi的な応用としてポジションを担保に借り入れを行う仕組み(例:Gondor)や、UMAやAugurといった解決プロトコルによる結果確定の仕組みも存在します。最後に、データ分析やUX補助、可視化といったツール類が、利用者体験を補強する役割を果たしています。
見えてきた構造
現状では、大きく二つの陣営が形成されています。ひとつはPolymarketやKalshiを中心とする既存市場寄りのグループで、既存の流動性や配信チャネル(XやDiscordなど)を取り込む形で成長を目指しています。もうひとつは新興でニッチ特化型のグループで、特定のテーマに焦点を当てつつ、将来的にはよりオープンな市場構造を構築しようとしています。
また、DeFi的要素であるAMMや流動性提供(LP)、借貸といった仕組みはまだ十分に活用されておらず、今後の拡張余地が大きいとされています。最終的に成長のカギを握るのはユーザー数、流通量、そして流動性であることが明確になっています。
まとめ(TL;DR)
予測市場は依然として初期段階にあり、今後DeFiと同様に大きな拡大余地を秘めています。市場構造はPolymarket系の主流陣営と、テーマ特化型のニッチ陣営という二極化が進行しています。次の成長ポイントはDeFiとの連携を強めつつ、いかにして流動性とユーザー基盤を確保するかにかかっています。
▍Soneiumが、新しく「Soneium Score」というユーザー活動を評価・報酬する仕組みを導入
Soneium Scoreの概要
Sonyが手がけるSoneiumブロックチェーン(Ethereum L2)は、新しく「Soneium Score」というユーザー活動を評価・報酬する仕組みを導入しました。これはオンチェーンでの行動履歴をスコア化し、ユーザーの参加意欲を高めることを目的としています。
Soneium Scoreの仕組み
Soneium Scoreはユーザーの行動を4つのカテゴリで評価し、スコア(ポイント)を付与します。評価対象は、デイリーアクティビティ(連続ログインや利用)、流動性提供(DeFiでの資産供給など)、NFT保有状況、そして特定プロジェクトとの提携イベント参加といったボーナスアクティビティです。これにより、資産のスワップ、ステーキング、NFT取引など幅広い活動が「評判」や「実績」として積み上がる仕組みになっています。
狙いと課題解決
Soneiumが指摘する課題は、ユーザーの「評判」や「信頼」を継続的に測る仕組みが欠けていること、そしてプロジェクトが「本当にアクティブなユーザー」を惹きつけにくいことです。Soneium Scoreの導入によって、ユーザーは自分のオンチェーン活動を証明できるID(reputational identity)を持つことが可能になります。これによりプロジェクト側も、積極的に活動しているユーザーを見極めやすくなるという利点があります。
今後の展開
Soneium Scoreは「Season 1」として、DeFiやゲーム、デジタルコレクティブルなど複数のパートナーと連携して展開されます。ユーザーは初期段階から多様なアプリでスコアを稼ぐことが可能です。テスト段階ですでに1400万ウォレット以上が参加しており、Sonyグループの強力なブランド力とユーザーベースを背景に、エコシステムの拡大が期待されています。
まとめ(TL;DR)
SoneiumはSonyが開発するEthereum L2であり、その新制度であるSoneium Scoreはユーザー活動を可視化・スコア化し、報酬につなげる仕組みです。ユーザーは日々の利用や流動性供給、NFT保有などによって評価を積み上げることができます。これは「ブロックチェーン上の信用スコア」として機能し、ユーザーとプロジェクトの双方にメリットをもたらす可能性があります。
▍「バッファロー・ビル」ベッセントのステーブルコイン戦略 by Arthur Hayes
概要と戦略の位置づけ
この記事では、トランプ政権の財務長官であるScott Bessent(スコット・ベッセント)が「バッファロー・ビル」と称される大胆な金融戦略について論じられています。その戦略とは、ユーロダラー(米国外の銀行に預けられた米ドル)やグローバルサウス諸国の預金を取り込み、米国の財政赤字を補うというものです。ベッセントはユーロダラー銀行システムを弱体化させ、海外の非ドル預金を米ドル建てステーブルコインに誘導することで、米国国債に対する「価格非感応的(price-insensitive)」な買い手を確保しようとしています。
この戦略を支えるのはWhatsAppやXといった米国のソーシャルメディア企業です。これらの企業がクリプトウォレットを統合することで、各国の規制当局が十分に対応できない形で、ドルへのアクセスを望むグローバルサウスのユーザーにステーブルコインを普及させる可能性があります。
DeFiプロジェクトへの波及
著者は、このトレンドがDeFi(分散型金融)の主要プロジェクトの成長を牽引すると予測しています。具体的には、Ethena、Ether.fi、そしてHyperliquidが大きな受益者になると見られています。
Ether.fiは、ユーザーがステーブルコインを預け入れ、Visaカードとして利用できるソリューションを提供し、世界中の人々の消費行動を促進します。Ethenaは、ステーブルコインをデリバティブ取引に貸し出すことで、従来の国債利回りを超える収益機会を提供します。そしてHyperliquidは、ステーブルコインの大量流入を背景に、Binanceを凌ぐ世界最大のデリバティブ取引所へと成長すると予測されています。
新たな金融アーキテクチャの形成
このような流れによって、DeFiは数兆ドル規模にまで成長し、新たな金融アーキテクチャを形成する可能性があると指摘されています。著者は、自身の投資先でもあるこれらのプロジェクトを「この巨大な変化から利益を得るDeFiの柱」と位置づけています。特に、未公開のステーブルコインインフラプロジェクト「Codex」にも大きな期待を寄せており、その潜在的な役割は今後のDeFiエコシステムにおいて重要になると見込まれています。
▍DragonflyのHaseeb氏によるWebX東京参加後の所感
日本市場の潜在力
日本はGDP規模でドイツやインドに匹敵し、韓国の2倍以上の人口を抱える潜在的に巨大な市場です。しかし現状では世界的な暗号資産企業が少なく、リテール投資家の取引参加率も低い状況にあります。日本の参加率は約5%にとどまり、韓国の約25%と比較すると大きな差があることがわかります。
最大の障害は税制
日本市場が伸び悩んでいる最大の理由は税制です。暗号資産の利益は給与所得と同じ「総合課税」に分類され、最大で55%もの税率が適用されます。これは株式譲渡益課税(20%)と比べて極めて不利です。さらに以前は「含み益課税」も存在しており、国内でのTGE(トークン発行)はほぼ不可能でした。現在は撤廃されたものの、高税率が依然として大きな参入障壁となっています。この影響から、MetaPlanet株のように「法人を通じたBTC保有」が税制上優遇され、株価が純資産価値(NAV)を上回って取引される現象も見られます。
政治的な雰囲気の変化
一方で、政治的な動きには変化が出ています。首相や財務相がWebXに登壇し、税制改革を約束する姿勢を示しました。ただし実際に制度改正が行われるまでには1年以上かかる見通しです。全体的に、アメリカの政策転換を受けて日本もそれに追随している印象があります。
日本ならではの特徴
日本市場には他国と異なる特徴が存在します。まず、コーポレート主導である点です。SBI(Ripple投資)、ソニー、セガ、野村など大手企業が積極的に動いており、多くの国で見られるリテール主導の状況とは対照的です。また、NFTやIPのトークン化に注力しているのも特徴的で、知財輸出大国としてIPのマネタイズを強化しています。さらに金融面では円建てステーブルコイン「JYPC」が承認済みですが、普及はまだ限定的です。リテールの嗜好においては、XRPとADAが圧倒的に人気を集めており、独自のコミュニティを形成しています。
展望と課題
今後税制が整備されれば、日本における暗号資産の採用は加速する可能性が高いです。しかし企業やプロジェクトが参入するためには、ローカライズや現地での営業活動、さらに強力な国内パートナーの確保が必須条件となります。日本市場は欧米や韓国とは文化的に大きく異なるため、後回しに扱うと失敗するリスクが高いと考えられます。
まとめ(TL;DR)
日本は「規模は巨大だが税制に縛られていた市場」です。規制緩和が進めば、企業・IP・ステーブルコインを軸に、一気にグローバル暗号資産市場の主要プレイヤーに浮上する可能性があります。