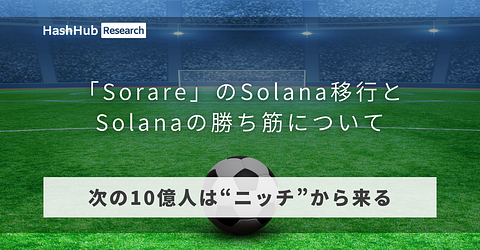Solanaの経済モデルを再構築する「SIMD-228」— 進化か、それとも岐路か
2025年03月07日
リサーチメモ(masao i)
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
※免責事項:このレポートは部分的に生成AIで作成されており、査読は行われていますが必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
Solanaコミュニティで賛否を呼んでいる提案「SIMD-228」が、まもなくバリデーターによる投票にかけられます。(エポック753で実施)
(※25年3月10日追記|「SIMD-228」の現在の投票状況はflipsideにてPine Aanalytics追跡してまとめています。:https://flipsidecrypto.xyz/pine/simd-0228-voting-metrics-Fe6ZCP)
(※25年3月14日追記|「SIMD-228」賛成票が閾値に達せず否決:https://x.com/DegenerateNews/status/1900345446637212057)
この提案は、Solanaのインフレ(新規発行)モデルを抜本的に見直し、SOLの新規発行量(インフレ率)の決定方法を大きく変更しようとするものです。
この記事では、過去2ヶ月をかけて賛否ありながらも公開討論が続けられてきた提案「SIMD-228」の具体的な内容や狙い、ネットワークのインフレ率への影響、さらにメリット・デメリットについて、カジュアルな視点で分かりやすく解説します。
SIMD-228を一言で言えば、「セキュリティ維持に必要な分だけ発行し、余計な供給を抑える」という大胆(やや過激ともいえる)な提案です。しかし、その革新性ゆえに、想定されるリスクや未知のリスクを含め、懸念の声も少なくありません。
それでも、この提案を推し進めようとする人々がいるのも事実。では、彼らが期待する利点とは何なのか? その賛成派・反対派の視点と背景を整理するために、「SIMD-228」まとめをAIを活用して作成しました。
以下、ご参考ください。